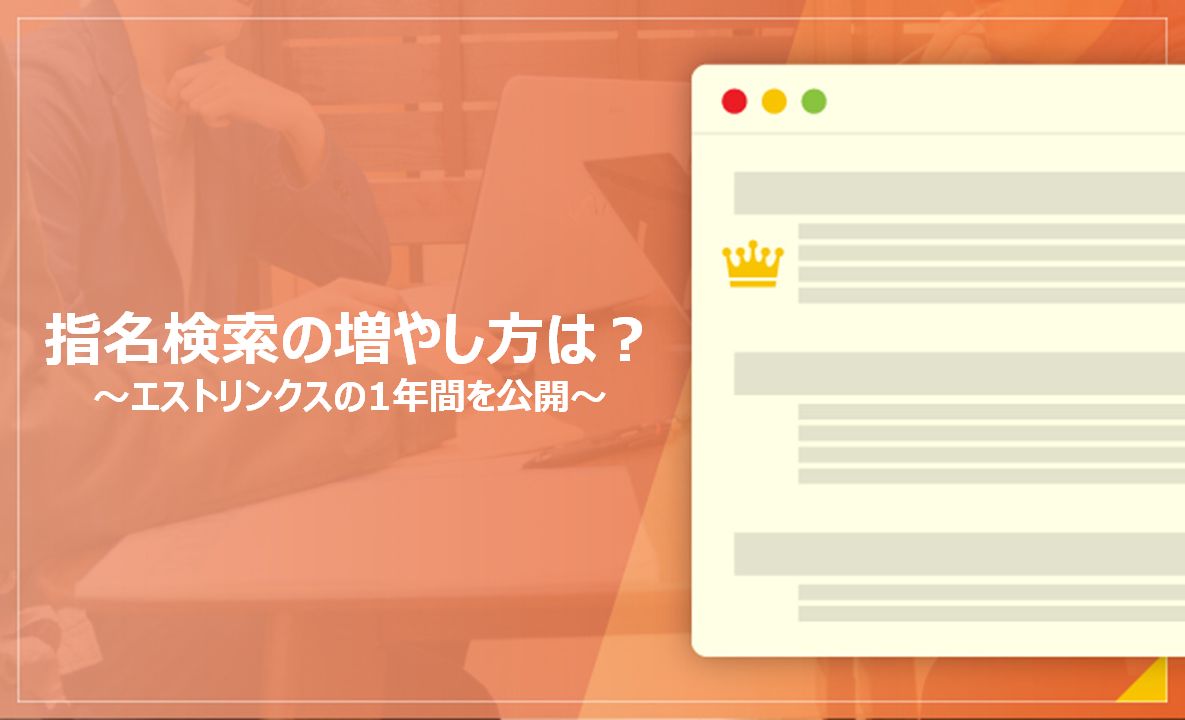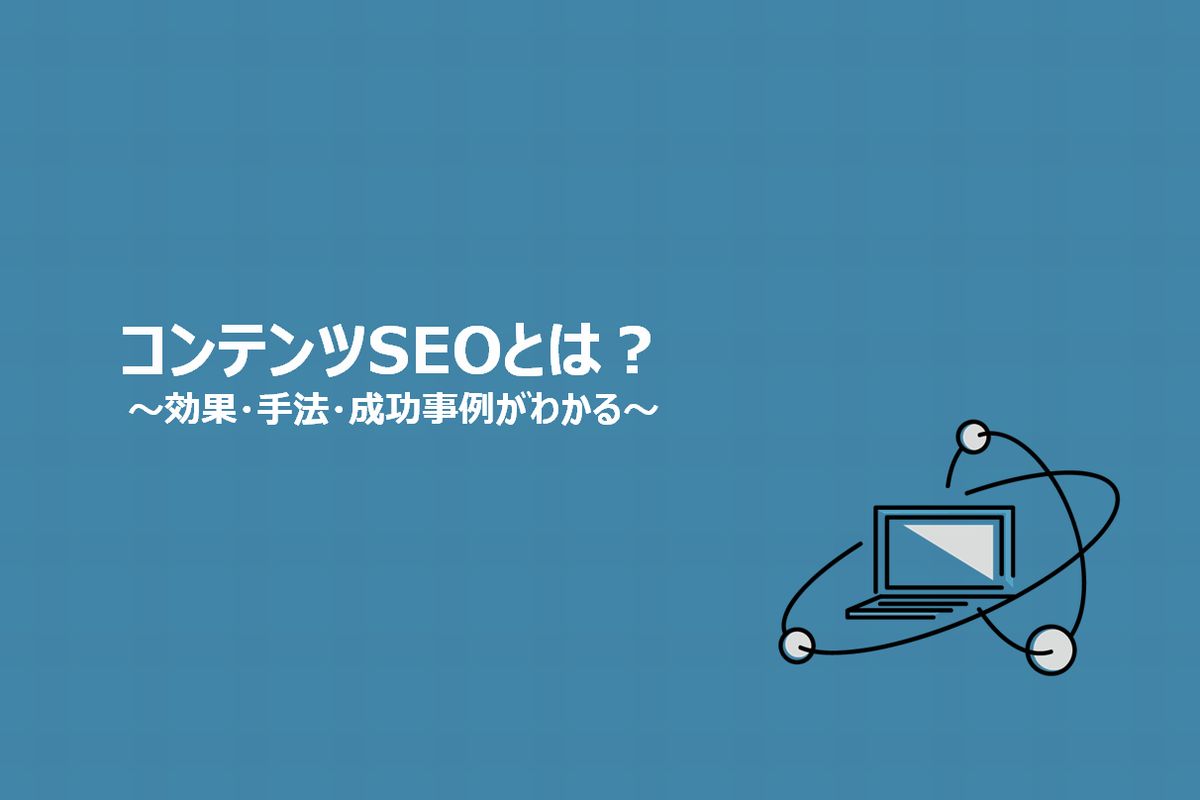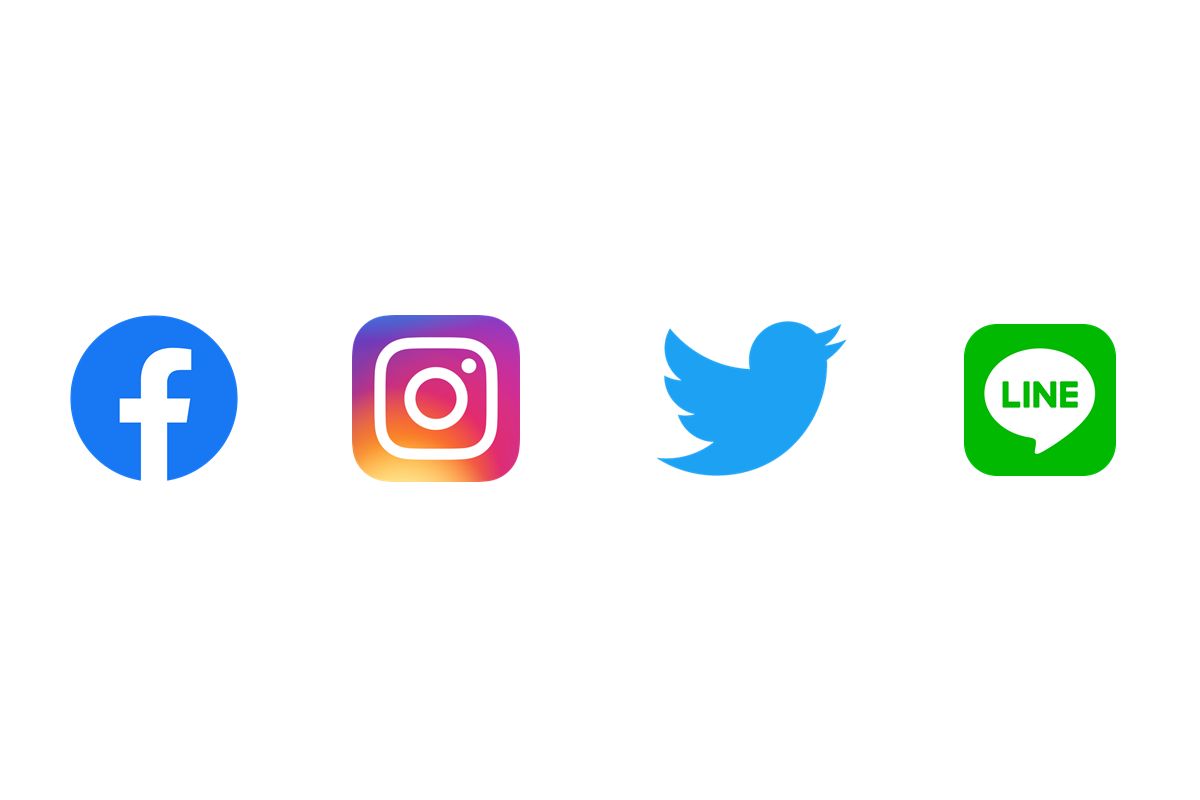「です・ます調」(敬体)と「だ・である調」(常体)の使い分けやルール、だ・である調に似ている体言止めの扱いはどうなるのかについてご紹介します。
Contents
それぞれの特徴と向いている文章

です・ます調(敬体)の特徴
です・ます調は、語尾が「です」「ます」「でしょう」「ましょう」「ません」などになります。相手が「ですよね」「ますよね」という口調で話してくると、落ち着いた印象を持ちやすいのと同様に、です・ます調で書いた文章は、全体的に柔らかく丁寧な印象になります。
使われるシーン
・企業紹介記事
・文書
・解説文・説明文
このサイトはライター募集のために作られていますが、お役立ちコラムも充実しています。
だ・である調(常体)の特徴
だ・である調は、語尾が「だ」「である」「だろう」「ではない」などになります。だ・である調で書いた文章は、少し語気が強く固い印象になり、専門的な内容や主観的な見解と相性が良いです。
使われるシーン
・体験談
・個人ブログ
・論文
このサイトはライター募集のために作られているが、お役立ちコラムも充実している。
ひとつの文章で交ぜてはいけない

文章を書く上での大前提として、です・ます調と、だ・である調、どちらか片方に統一する必要があります。文章単位でももちろんですが、サイト全体でも統一する必要があります(サイト内に体験談が含まれる場合は除く)。
両者が入れ替わり立ち替わり登場すると、リズムが悪くなることに加え、読者に稚拙な印象を与えてしまうためです。また、語尾が統一されていない記事は、読んだ時にまとまりがない印象になってしまいます。
記事を書くときに重要なのは、読み手への思いやりである。どんな悩みをもってこの文章を読んでいるのか、きちんと理解する必要があります。そのため、記事を書く前の段階で読者の行動のリサーチや、伝えるための文章構成を入念に考え込むべきだろう。この点に気をつければ良い記事に一歩近づけるはずです。
例文は「だ・である」⇒「です・ます」⇒「だ・である」⇒「です・ます」と展開している文章です。どんな人格の人が誰に向けて書いたのかよく分からない文章になってしまっています。文章を書くときには、です・ます調と、だ・である調どちらで書けばよいか指定があるため、必ず統一するようにしてください。
ただし例外があります。以下の条件では、両者を交ぜても問題ない場合があります。
箇条書き
箇条書きは、要点を簡潔にまとめるためのものなので、です・ます調で書かれた文章に登場する場合も箇条書き部分だけ、だ・である調で書いて問題ありません。
セリフ
悩みをわかりやすく提示するためにセリフを使うことがあります。このような場合は、口語体を使った方がリアリティが出るため、両者が交ざっても問題ありません。
「最近筆が乗らない」「ネタが思い浮かばない」。こんな悩みをお持ちの方は環境を変えてみてはいかがでしょうか?
だ・である調部分の強調
※ご依頼いただく案件の性質上、エストリンクスでは基本的に禁止している手法です。
だ・である調を意図的に織り交ぜて、文章のリズムを変えたり強調したりします。そこまで「です・ます調」だった文章のリズムを意図的に崩せるので、読者にとって印象深く、共感を求めたり訴求したりする力が上がります。
ただし、強調が多いと不自然になるため、多くても1,2回に留めます。
私はこれらからもライターを続けていきたいと思っています。自分の書いた記事が誰かの役に立っている……。これだけでもライターを続ける十分な理由です。
一文内での混在に注意
意外に多いのが、一文内にです・ます調と、だ・である調が交ざってしまうケースです。例えば以下のような状態です。
私は文章中の口語体に気を付けているが、たまに交ざってしまいます。
「気を付けているが」の部分はだ・である調なのに、語尾はです・ます調になっていますね。気を付けて入ればすぐに気づきますが、走り書きをするとたまに交ざってしまうことがあるので注意しましょう。
メインはです・ます調
記事作成は、レギュレーションで、です・ます調と決められている案件がほとんどで、だ・である調の案件は非常に稀です。
だ・である調よりも、です・ます調の方が柔らかく読みやすいため、不特定多数の人に見られるwebとの相性が良いのです。
基本的にはレギュレーションの目立つ位置に記載されているので、作成時に確認しましょう。
です・ます調での体言止めの扱い
体言止めとは、文を名詞で終わらせる表現技法です。柔らかい印象が強くなり、リズムも良くなります。
毎日しなければならない家事。ひとつひとつに時間もかかるため大変です。そんな家事にかかる時間を短縮する方法をご紹介します。
家事は毎日しなければならないものです。ひとつひとつに時間もかかるため大変です。そんな家事にかかる時間を短縮する方法をご紹介します。
です・ます調と指定されている場合も、体言止めは使って問題ありません。ただ、体言止めが2文以上連続すると、不適切に柔らかい文章になってしまいます。使用する場合は要所に挿む程度にしておきましょう。
また、案件によっては、体言止めの使用を禁止している場合もあります。体言止めの禁止は特殊な仕様なので、要望は必ずレギュレーションに書いてあります。誤って使用してしまわないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。
関連記事:体言止めとは?例文・使い方・効果やビジネス文書で使うときの注意点
まとめ
です・ます調と、だ・である調の使い分けについて解説しました。文章を書くことに慣れていると「統一するのは当たり前」とも思ってしまうのですが、文章に触れる機会があまりなかった方は、気付かないうちに両者を交ぜてしまうことがあります。ただ、意識して文章を書いていればすぐに慣れます。両者が交ざっている文章を「気持ち悪い」と思えるようになるまで、とにかくたくさん書くのがおすすめです。
他にも、記事作成に使えるテクニックやレギュレーション、構成案を考えるコツをまとめました。「よりいい記事を書きたい」とお考えのライターさんは、ぜひ以下のページもご覧ください。
CONTACT
コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。
また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。