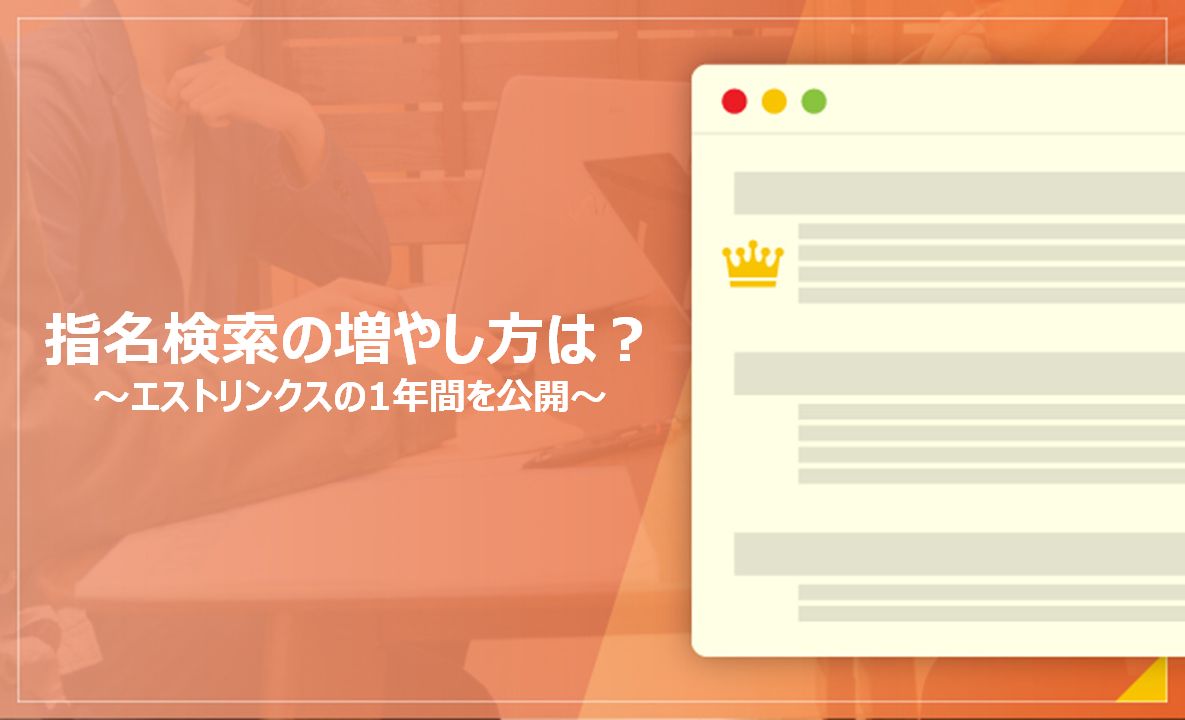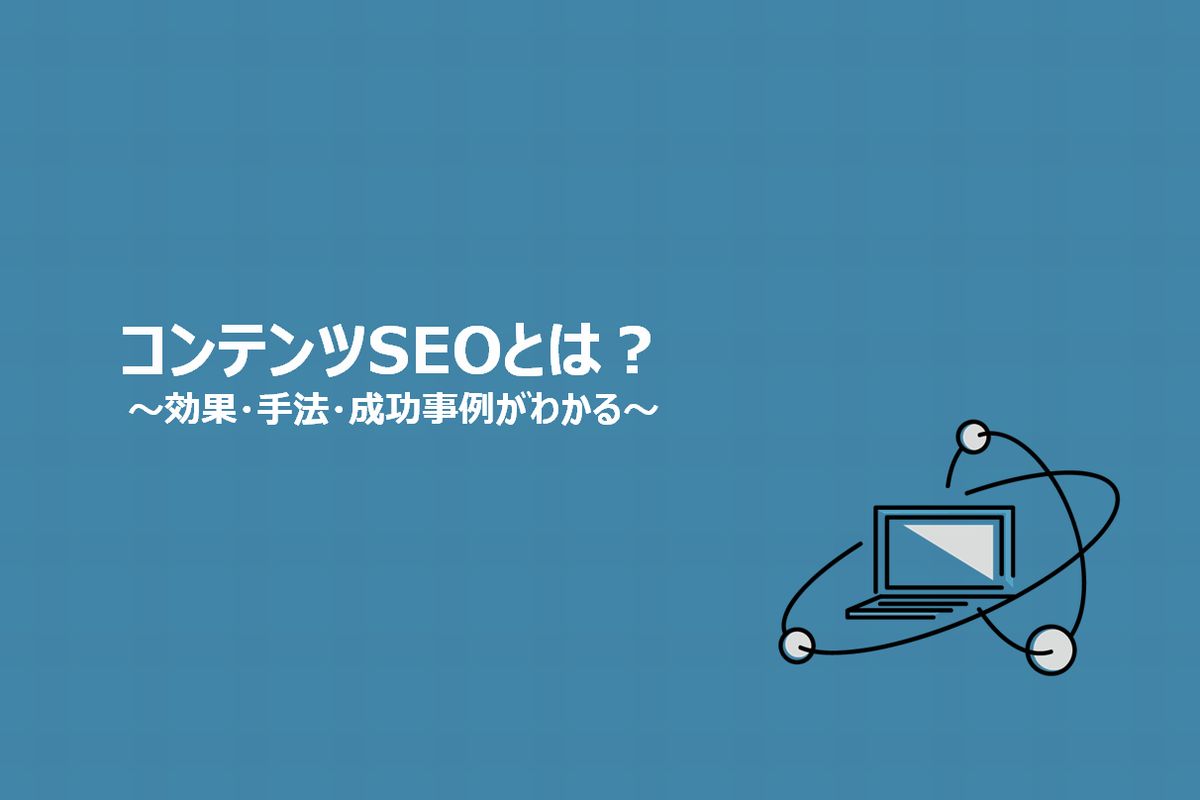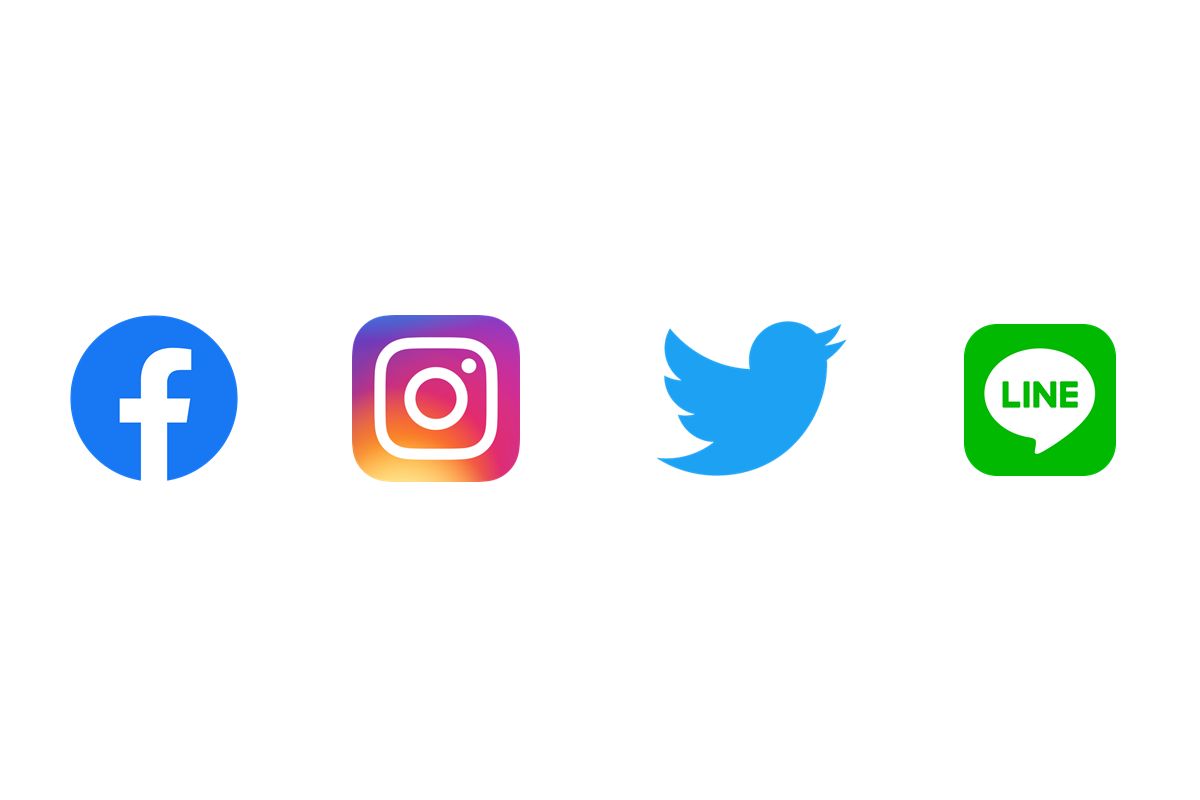突然ですが、自分に文章力が足りないと感じてしまうことはありませんか?
そんなあなたは、文章力を向上させたいと思いつつ、何をすればいいのかわからずに悩んでいるでしょう。
実はポイントを押さえてライティングを行えば、比較的短期間で文章力を向上させることができます。私はこれまで長くライター業に携わっていますが、まだまだ自分の文章力に満足していません。ですがライター初心者時代に取り組んだ様々な試行錯誤が、今になってライティングのスキルに繋がっていると感じています。
今回は、私が文章力向上のために気にかけていることを、10個ご紹介します。簡単な内容で、基本的なことばかりですが、参考にしていただけたら嬉しく思います。
Contents
1.小さな積み重ねが文章力を向上させる
私の経験上、ブログや記事の文章力は、文才ではなく日々の鍛錬の積み重ねによって磨かれるものだと感じています。なぜなら、一人でも多くの人に自分のライティングを読んでもらうためのポイントは、コツを掴むことにあるからです。
特にWEBライティングにおいて、これらはかなり重要な要素です。なぜなら、読者が「このブログは面白くないな」と感じた瞬間に、別の記事を探すことができるからです。
書籍や新聞の場合、購入という段階を踏んでいますし、他に興味をそそられる本を探すのが面倒だったりするので、それでも根気よく読み続けてくれる人はいるでしょう。しかし、WEBライティングの場合はタダで読めることが多いもの。なにより、すぐに他の記事を探すことができるため、読みにくい内容を一生懸命読み続ける必要があまりないのです。
「読み進めたくなる記事」「人気のある記事」には、一定の法則があります。たくさんの人に読んでもらえる記事を目指すためには、その法則を知り、日々の鍛錬の積み重ねによって、文章力を向上させることが大切です。
2.ライター初心者だった頃の私
ライター歴も長くなった今、こうして多くの方に読んでいただける記事を作成できるようになった私ですが、ライターを始める前は、実は皆さんと同じ全くのド素人。
それまで社内文章や企画書を作成することはあっても、出版物やブログを書いたことはほとんどなかったので、人に読んでもらうためにどんなことに気をつければいいのか、まったくわかりませんでした。
ライターを始めた当初は、ライティングの通信講座や資格を取ることも考えました。しかし内容を見て、「本当にこれで人に読んでもらえる記事が書けるのか」と思い、自分でトライアンドエラーを続ける道を選びました。

3.文章力向上のために気にかける10のこと
今回ご紹介することは、私が文章力を向上させるためにトライアンドエラーを重ね、培ってきた経験からきています。
それは文章を書くときに、気にかけていることです。結果的に、この気にかけていることが、文章力向上につながると考えています。
3-1.やさしい表現を心がける
記事内容はできるだけわかりやすくかみ砕いて説明すると、文章力が向上します。
難しいことを難しく書くことは、誰にでもできます。しかし、難しいことを万人にわかりやすく説明しようとするのはかなり難しいこと。言葉一つ一つの意味を正しく理解し、誰でもわかるような言葉やたとえを用いる必要があるからです。
難しい文章をわかりやすく書き換えることで、言葉の正しい表現や適切な言い換えの方法を身につけることができます。また、さまざまな情報を得ようとするため、視野も広がります。文章力を向上させるために、これほど訓練になることはありません。
わかりやすい記事を書くことは、読み手を惹きつけるという上でも重要なポイント。わかりやすい記事ほど、読み手の頭にすんなり入ってくるものです。
どんな専門的な文章でも、万人にわかりやすく書くことができます。まずは自分が「わかりにくい」と感じた記事を、かみ砕いて書いてみるところからはじめてみては。
3-2. 一文をできるだけ短くする
WEBに限らず、一文は短いほうが、相手に意味が伝わりやすくなります。できるだけ文章を短くするよう心がけましょう。
まずは下記の2つの記事を見てください。
《今日は新商品の多機能フライパンをご紹介します。焦げ付きにくいので目玉焼きなどもするっと取れますし、洗いやすいので主婦の人に大人気の商品です》
《今日は新商品の多機能フライパンをご紹介します。焦げ付きにくく、洗いやすいのが大きな特徴。こびりつきやすい目玉焼きなどもスルッと取れます。主婦に大人気の商品です》
どちらが読みやすいと感じましたか。おそらく後者ではないでしょうか。
自分の作成したブログや記事をよく見てください。一文の長さが蛇のように長ーく延びていませんか。言いたいことをたくさん書きたい気持ちはわかりますが、それでは読み手をイライラさせてしまうかも。
一般的に、理想的な一文の長さは40文字、長くても50文字と言われています。これはどんな記事にも言えることです。
読点(、)や接続詞を必要以上に盛り込んでいると、一文が長くなる傾向があります。意味の切れるところで文章を区切るなど、まずは読点や接続詞を減らすよう心がけてみましょう。
3-3. 見出しだけで段落の意味が伝わるようにする
見出しは記事の案内板とも言える存在です。見出しを見ただけで、その段落で何が言いたいのかがわかるよう心がけましょう。
例えば、料理の手順を紹介する記事を作成するとしましょう。見出しが「1」「2」などの単なる番号のみだった場合、次に何をするのかが見出しだけではわからないので、いちいち文章を読まなくてはなりません。もし読み手が私のようにせっかちだったら、とても面倒だと感じるかもしれません。
一方、もし見出しに「煮干しでダシを取る」「肉に下地をつける」などが書かれていると、見出しを見ただけで次に何をするのかが一目瞭然ですよね。
これは料理以外の記事にも言えること。特にWEBライティングの場合は、はじめに何が書かれているのかを読み手に伝えることが、最後までブログを読んでもらうための大きなポイントとなります。また、短い文章で意味を伝える訓練にもなります。
はじめのうちは他の人に記事を読んでもらい、見出しだけで意味がわかるかを聞いたほうがよいでしょう。

3-4.できるだけカタカナ語を使わない
一般的にカタカナ語と言われる言葉は、できるだけ使用しないよう心がけましょう。
カタカナ語とは、「スキーム(枠組み・仕組み)」「アジェンダ(議題・課題)」「ペンディング(保留・中止)」といった、カタカナで意味を伝える言葉。これらは実は、相手に意味が伝わりにくい言葉でもあります。
カタカナ語のいいところであり、悪いところは、意味をぼかして伝えることができること。しかし意味をぼかしている分、文章力が身につきにくくなります。また、相手にもぼやっとしか意味が伝わらなくなります。
またカタカナ語は、人によって意味の捉え方や印象が異なる言葉でもあります。例えば「ペンディング」には「保留」と「中止」の2つの意味があります。どちらの意味で捉えるかで、内容は大きく変わります。
カタカナ語の中には、そもそも意味があまり知られていないものも数多くあります。たくさんの人に読んでもらうための記事なのに、言葉の選び方で読み手の幅を狭めるのは本末転倒です。カタカナ語を多用するクセのある人は、日本語に直して書くことをクセづけましょう。
3-5.意味が曖昧な言葉はとにかくググる
これまでなんとなく慣習で使っていた言葉があるなら、意味をしっかり調べてから用いることをおすすめします。
例えば「姑息」という言葉、あなたはどのように使用していますか。多くのブログでは「卑怯・ずるい」と同様の意味で使用されていますが、実はこれは誤用。本来は「その場を逃れるための一時しのぎ」という意味で使われる言葉なんです。
ほかに誤用されやすい言葉として「煮詰まる」が挙げられます。「行き詰まる」などの意味で使われることが多いですが、本当は「結論が出かかっている」という意味の言葉です。
人によっては、「読み手の大半に意味が通じるならいいじゃないか」という意見もあるかもしれません。しかし、言葉を正しく使用していない記事は、それだけで説得力に欠けるものです。
文章力を向上させることは、なにも表現力を磨くことだけではありません。言葉を正しく使うことも、文章力を高めるために必要なことです。ライティングに力を入れるなら、普段何気なく使用している言葉の使い方にも気を使うようにしましょう。
3-6.適度に漢字を開く
「開く」とは、漢字をひらがなにすることを言います。漢字が多すぎると、読みにくい文章になりがちです。文章力をつけるなら、どの漢字を開くべきかを押さえておいたほうがよいでしょう。
例えば「○○して下さい」は、一般的に開いて使われることが多い言葉。開くと「○○してください」となります。他にも、一般的に開いて使われる漢字には「頂く(いただく)」「殆ど(ほとんど)」などがあります。
実はどの漢字を開くべきなのかについての、厳密な決まりはありません。出版社によっても異なるため、この点についてはさまざまな文章を読み、感覚をつかむしかありません。
ここでは一般的に開いたほうがいいと言われる漢字について、いくつかご紹介します。
・出来るだけ・出来る限り(できる)
・更に(さらに)
・様々(さまざま)
・何処(どこ)
・何時(いつ)
・如何(いかが)
・丁度(ちょうど)
・且つ(かつ)
・有る(ある)

3-7.文末を一辺倒にしない
文末を「です」「ます」の一辺倒で終わらせていませんか。より表現力の高い文章を作成したいなら、文末を一辺倒にせず、体言止めなどをうまく使用しましょう。
例えば下記の2つの文章を比べてみて、どちらのほうが表現力に富んでいると思いますか。
(1)北海道は豊かな自然に恵まれたエリアです。人口は東京都の半分以下ですが、日本一の面積を誇っています。
(2)豊かな自然に恵まれた北海道。人口は東京都の半分以下ですが、日本一の面積を誇るエリアとして知られています。
1は文末が一辺倒なので、2に比べて表現力に欠けている印象があります。同じ内容の文章を書く場合でも、文末を変えるだけでイメージはかなり変わります。特に長文のブログや記事を作成する場合は、文末にバリエーションをもたせると、より読みやすく魅力的なものに仕上がりますよ。
3-8.書いた次の日に読み返す
ブログは作成してすぐにアップせず、次の日まで寝かせてもう一度読み返してからアップするようにしましょう。
執筆中は「何を書こうか」「話をどう展開させようか」など、思いを巡らせながら書き進めるもの。そちらに意識が集中するあまり、漢字間違いや、客観的に見てわかりにくい表現などを多用していることがよくあります。
一日記事を寝かせることで、頭を冷静にし、より客観的に記事の内容を吟味することができます。まずは今日書いた記事を、明日試しに見てみましょう。意外と恥ずかしい間違いをしているかもしれませんよ。
3-9.本や新聞を読む
本や新聞は、正しい表現や万人にわかりやすい言葉で書かれています。毎日継続して読み続けることで、自らの文章力を向上させることができます。
特に新聞は、ライティングにとって参考になることが多いもの。一文を短くまとめている点や、言葉を正しい用法で使用している点などは、非常に勉強になります。
同時に、最近の情報などをチェックすることができるので、情報収集という意味でも読んでおいて損はない媒体です。
もし可能なら新聞を取るか、電子版で毎日情報をチェックするクセをつけることをおすすめします。

3-10.とにかくライティングする
最後のポイントは、なんといっても自分で実際に書くことです。いくらいい記事を読んでも、ポイントだけを押さえても、実際にライティングしなければ、自分の身になりません。
どんなに下手でも、うまくいかなくても書き続けること。そして、できれば第三者にフィードバックをもらい、改善を続けていきましょう。始めはうまくいかないかもしれませんが、継続することで文章力向上の大きな力になります。
まとめ|ローマ(文章力)は一日にして成らず(つかず)
「ローマは一日にして成らず」という言葉あるように、文章力の向上は、一日で成るものではありません。日々コツを掴み、実際にライティングを続けることで上達していくものです。
継続していくことで、上達はアクセス数や読者数に現れてきます。まずは今日からできることをはじめてみましょう。
御社のサイトに良質な記事コンテンツを追加しませんか?
コンテンツマーケティングにおいて、良質な記事は欠かせません。いくら記事を量産しても、記事の質が低いと思うような効果は得られません。高品質な記事を継続的に更新すること。コンテンツマーケティングにおいて、”良質な記事作成”が占める重要性は非常に高いものがあります。
弊社が提供する記事作成代行サービスは、この”良質な記事作成”に力を入れたサービスでございます。
CONTACT
コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。
また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。