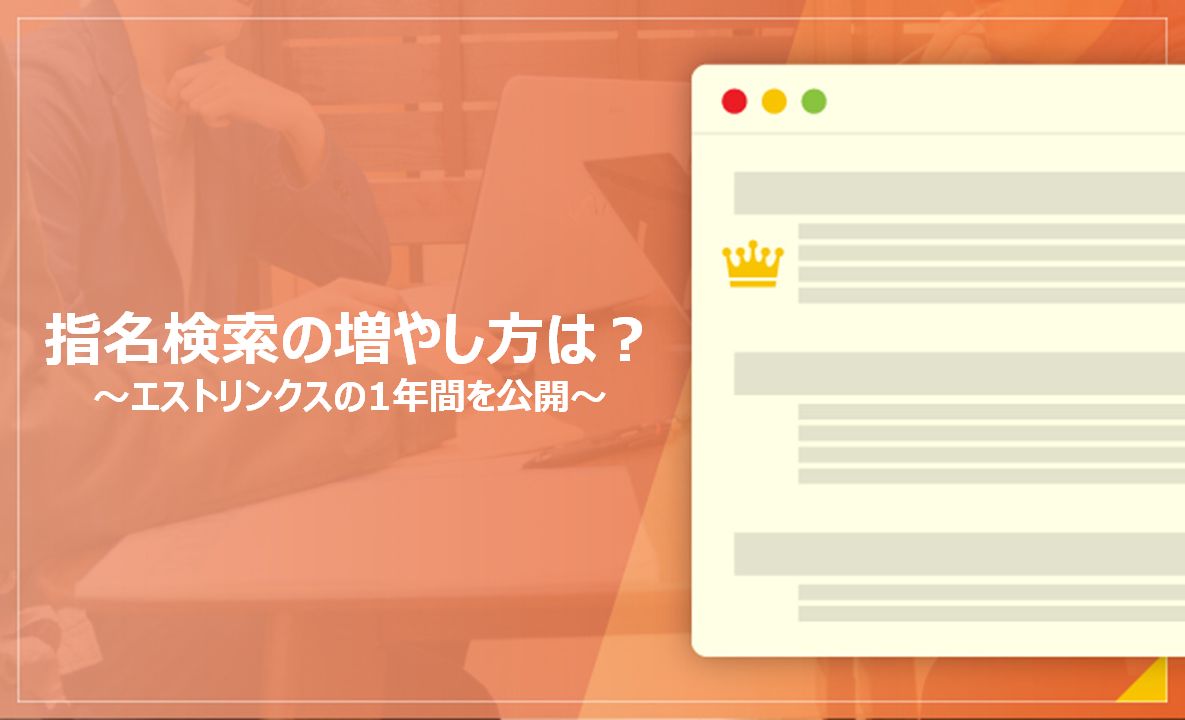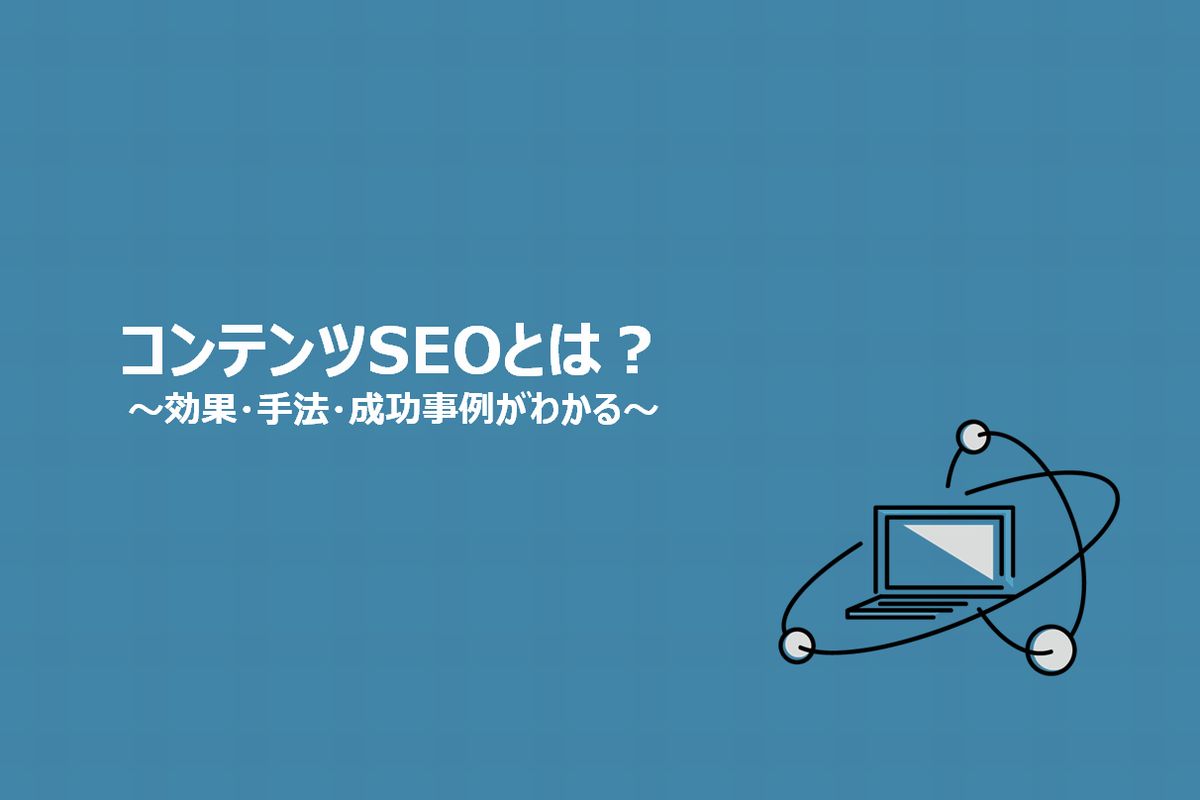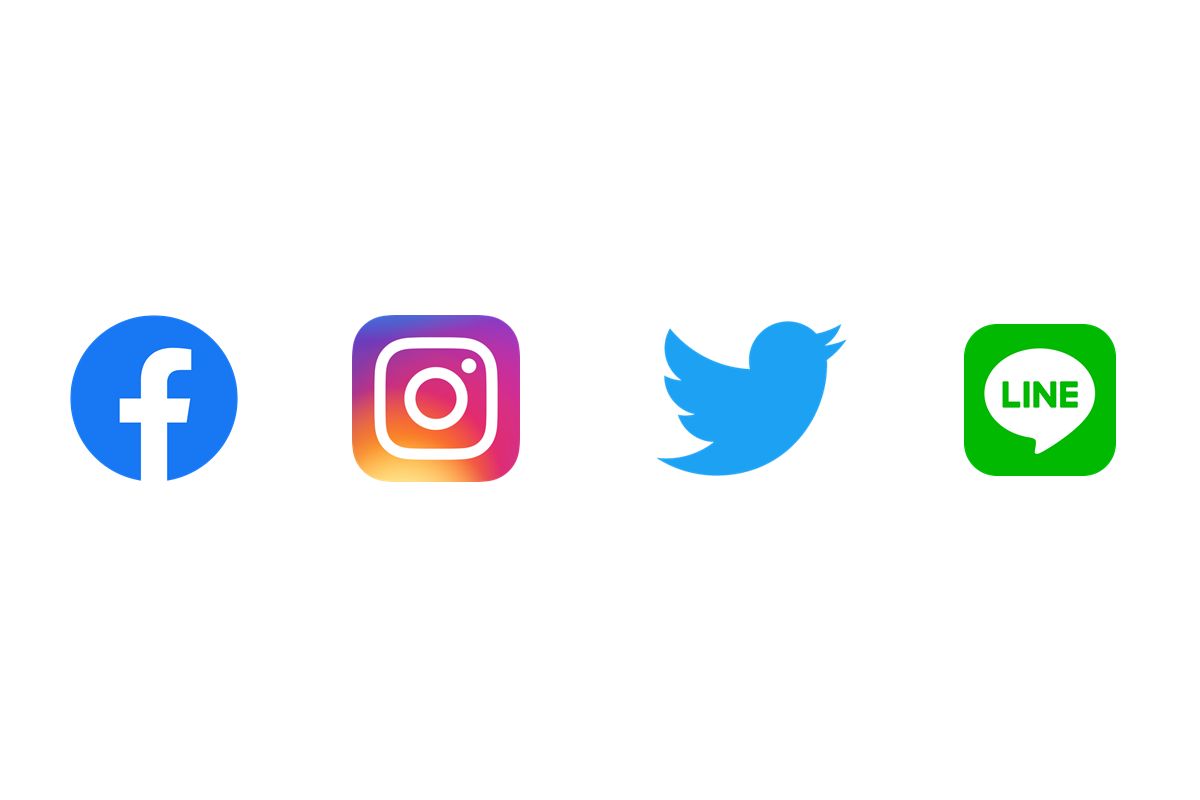私が「マーケティングオートメーション」という言葉を初めて聞いたのは、2015年の夏だった。
おそらく私が知るよりも前から、じわじわと業界に浸透していった言葉だと思うが・・・。
「マーケティングオートメーション」の概念は理解できても、それがいったいどのように会社内で使われるのか、当時の私はイマイチ理解ができなかった。
(それから半年くらい経った、ある日。)テックブックのクライアントには、お付き合いを始めてからマーケティングオートメーションを導入した企業もある。
マーケティングオートメーションを導入した担当者から直接お話を伺えたことで、少し理解が深まった。(クライアントは、B to B事業を行っている会社)
-----------------------------
Mさん「まー。導入してみないとわかりませんが、営業に良いパスを出せるかが勝負ですね。」
T(私)「パスというのは、どういった意味ですか?(営業がどう関わるのだろう?)」
Mさん「今はまだ構想段階なんですが・・・。リード顧客にメールマーケティングをして・・・スコアリングしてホットリードが出てきたら、営業チームにパスを出したいんです。
これ、ホットリードだよーといった具合に。で、あとは営業が従来通りに、電話していきます。」
T「なるほど。リード顧客を増やしてリードナーチャリングをして、最後のゴールは営業が頑張るんですね。」
Mさん「そうです。そこまで設計できれば、あとはどんなコンテンツでどうマーケティングしていくか、といった点をもっと深く考えないとなりませんね。」
T「リード顧客をホットリードにするためには、どんな人に、どのようなコンテンツを届けるかが重要になりそうですね。」
Mさん「ですね・・・。営業にパスを出すと言っても、何も考えずにメールを送っていてもホットになるわけないですからね・・・。
せっかくマーケティングオートメーションツールを使っているので、マーケと営業の間の谷をうまく越えられるような、良いパス出していきたいです。」
-----------------------------
・・・マーケティングオートメーションを初めてイメージした時は、「リード顧客の創出(オウンドメディア)→リードナーチャリング(メール)→問い合わせがきて受注」と勝手に想像していた。
しかし、よく考えてみると、製品の説明もなく、検討段階におけるコミュニケーションもない中で受注できるとは考えにくい。
Mさんが教えてくださったように、マーケティング部署と営業部署の連携が必要で、どんな人に、どのようなコンテンツを届けるかが重要なのだ。
つまり、(特にB to Bにおいては)マーケティングと営業の間の谷をうまく越えないと、マーケティングオートメーションが力を発揮することはできない。そう言っても良いのかもしれない。
もしかしたら、その谷とは、うまく越えられなければ成果が出ない「死の谷」なのかもしれない。
文/テックブック清水拓也
CONTACT
コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。
また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。