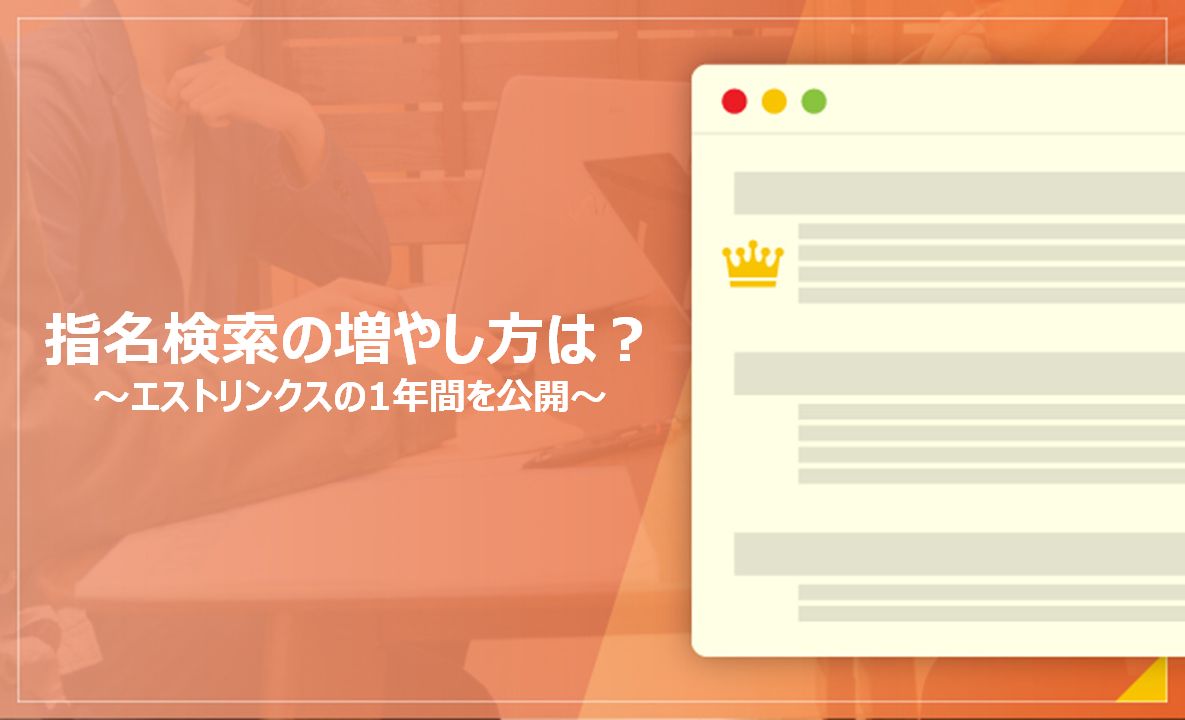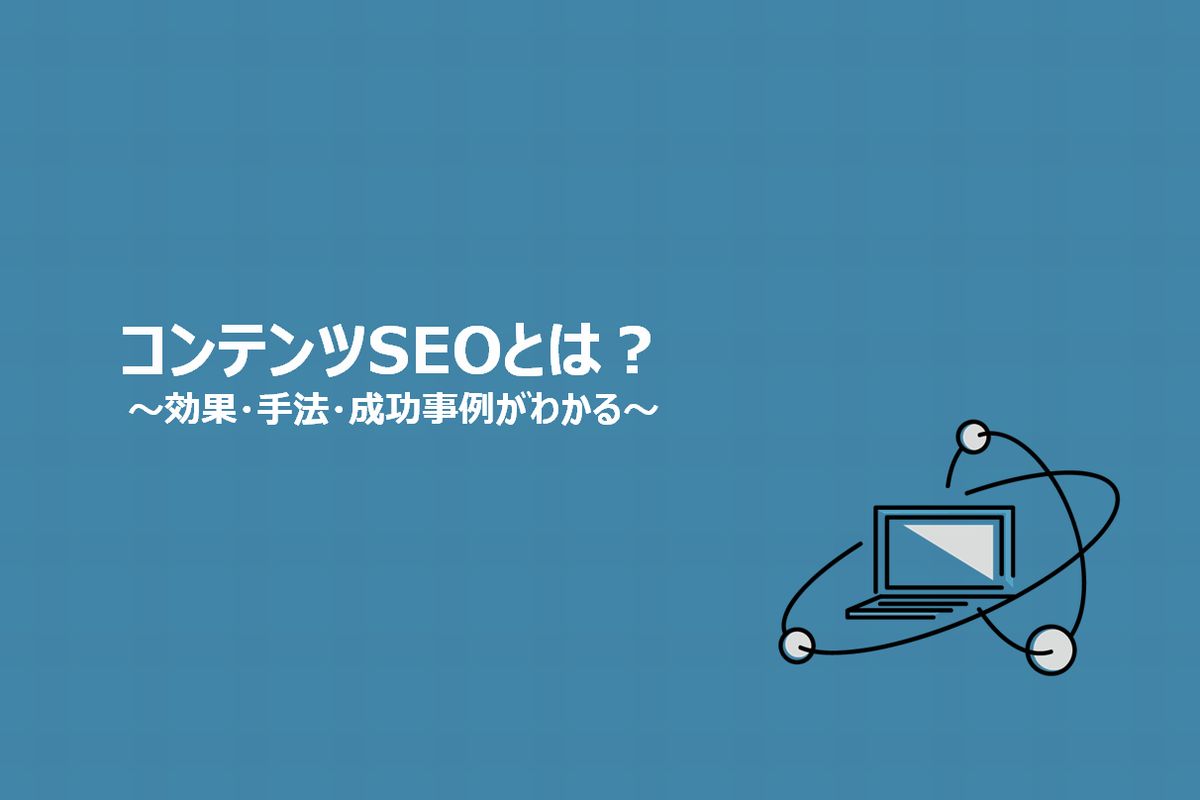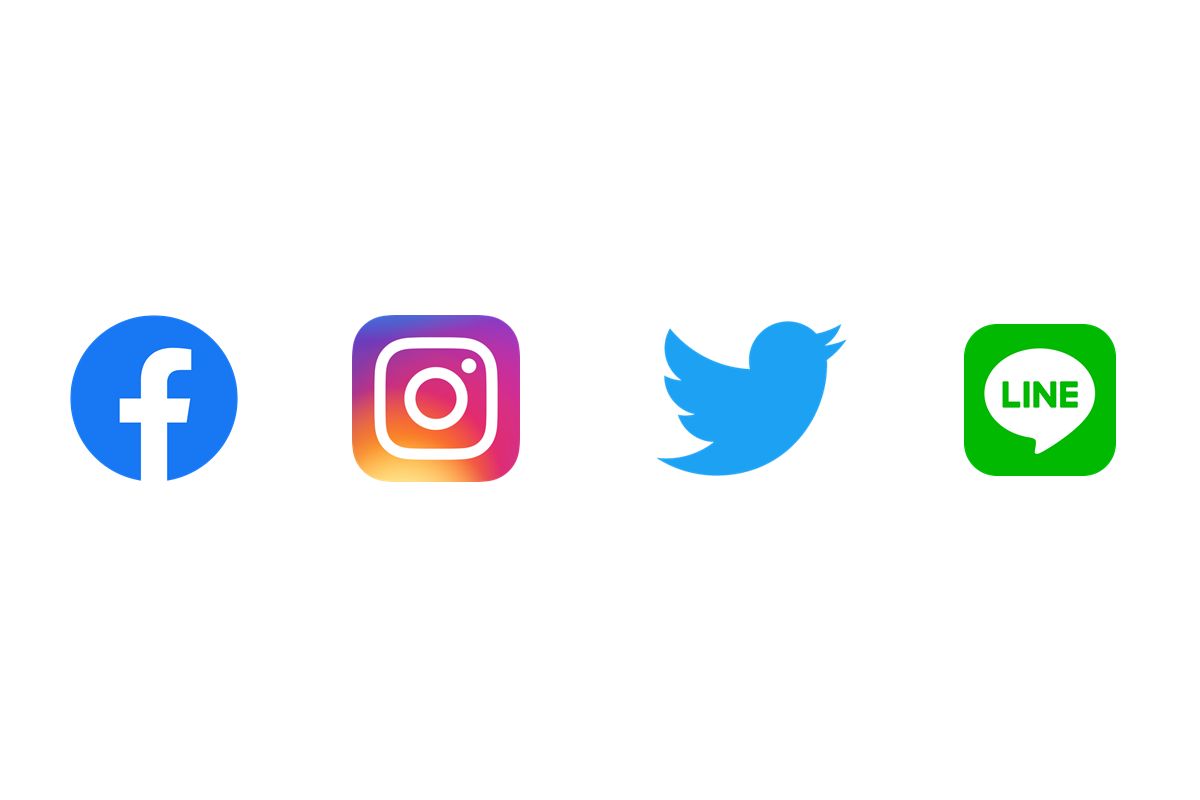今回はコンテンツマーケティングのありがちな失敗例を紹介します。
筆者自身が過去に経験した失敗にはじまり、初心者がつまづく失敗パターン、そしてオウンドメディアの構築・運営のサポートをする中で出会った事例の中から、ありがちなもの18個をまとめました。
コンテンツマーケティングが注目度を集めはじめたのは、2012年頃。当時はまだ先行事例が少なかったので、先人たちは希少な海外事例を参考に、手探りでその手法を確立していきました。しかし、今は先行事例も多数あるので、まずはそれらを参考にしましょう。
そして中でも、失敗例は貴重なケーススタディとなります。
成功を再現するのはとても難しいことですが、失敗例を知れば対策を立てることができるからです。知って得をするかは分かりませんが、知らないと損をする!・・・かもしれません。(なお本記事の失敗例の意味合いは、コンテンツマーケティングを即終了せざるをえないものではなく、修復可能だけど、知っていれば避けられた事例を失敗事例を呼んでいます。ご了承ください。)
※事例共有の参考記事はこちら
「注目ベンチャーの秀逸オウンドメディア事例9選」
「コンテンツマーケティング事例厳選15選」
1. コンテンツマーケティング運用の失敗例
いざオウンドメディア構築が完了して、実際にコンテンツマーケティングを運用していく中での失敗事例です。ただ正確に言うと、コンテンツを配信する前の段階が非常に重要です。さらに、運用をつづけながら実感することも多々あるので、想定通りにいかない場合も辛抱強く継続することが大事です。その点を意識しながら、失敗事例をご確認ください。
1-1. コンセプトが曖昧だった
コンテンツマーケティングの注目度が高いからと、曖昧なコンセプトのまま見切り発車してしまう失敗事例です。何事もそうですが、何かを感覚的に決めることはリスクを伴います。そして当然、コンセプトが曖昧であれば、後述するターゲットもKPIも曖昧になります。

よく人に何かを伝える時に「5W2Hが大事」といった言葉を聞きますが、コンテンツマーケティングにおいても同様です。誰に、何を、どうやって、どのように、どこで、いつまでに、いくらで?といった各質問の答えを用意することで、ぐっとコンセプトが明確になります。
コンセプトが曖昧なまま運用を開始すると、あとから修正することは簡単ではありません。コンテンツマーケティングをはじめる際は、必ず事前にコンセプトを詰めましょう。
※コンテンツマーケティング開始前に「5ヶ月で100万PVのブログを作成する為に実践した32の手順」(バズ部)は必読です。コンセプトのみならず、多くの学びがあります。
1-2. ペルソナ設定が甘かった
ペルソナは5W2Hの中の「Who?=誰に?」にあたります。その「誰に?」が不明確なままコンテンツマーケティングを開始してしまった失敗事例です。各コンテンツは誰に向けて書かれたものか?といった質問に対して、運用の主体者は明確に答えられないとなりません。
まれに「男性・30代前半」といった性別・年齢をペルソナに挙げる方がいますが、ペルソナは性別・年齢のセグメントのことではありません。できるだけ詳細に設定して、運用開始後も確認しつづけることが大事です。
1-3. コンテンツマーケティングをする目的設定ができていなかった
そもそもなぜコンテンツマーケティングを開始するのか?そして何を達成したいのか?といった目的をきちんと設定しなかった失敗事例です。
なぜ目的設定が重要かと言うと、それによってコンテンツマーケティングの戦略が変わるからです。例えばブランディング・自社サイトのアクセス獲得・自社商品(サービス)の見込み顧客獲得など、コンテンツマーケティングを運用する目的は多岐に亘ります。
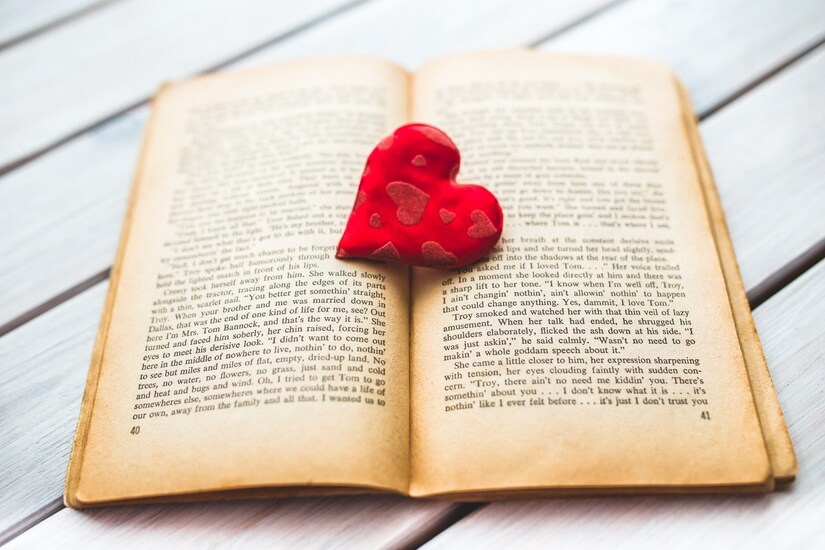
分かりやすい例を挙げると、認知向上を目的とするなら、拡散されやすいコンテンツを書く必要があります。タイトルも拡散を狙うキャッチーなタイトルが必要ですし、ソーシャルメディア運用の重要度が高くなります。
一方で、目的が「見込み顧客獲得」であれば拡散される必要性は低くなります。なぜなら適切なSEOキーワードを設定して、上位表示をさせれば少ないページビューでも見込み顧客にリーチすることができるからです。コンテンツマーケティングの運用において目的を明確にすることは、戦略を決める上で非常に重要なことです。
1-4. コンテンツマーケティングの主体者を明確にしなかった
コンテンツマーケティングをチームで運用する場合、成果を出そうとするなら片手間でやることは推奨できません。例えばECサイトを運営しながらコンテンツマーケティングにチャレンジするケースにおいても、必ずECサイト運営者とは別にコンテンツマーケティングの主体者を明確にして権限と責任を与えるのが良いでしょう。(既存のFacebook・Twitterアカウント運用の担当者にコンテンツマーケティングを兼任させるなど、コンテンツマーケティングと親和性が高い業務を掛け持ちさせるのであれば、その限りではありません。)
またチームで運用する場合、コンテンツを複数人で更新することになります。コンテンツマーケティングの運用を継続する中で「誰が、いつ、どんなコンテンツを更新するのか?」といった指揮をとることは、主体者の役割でもあります。主体者が明確でないと、この点が曖昧になり、継続的な更新が難しくなる可能性があります。
1-5. 適切な運用メンバーを用意できなかった
コンテンツマーケティングを開始したものの、チームビルディングがうまくいかずに継続的な更新ができなくなる失敗事例です。筆者の見解としては、「主体者を明確にする」よりは失敗の可能性が低いと考えますが、それでもメンバー選定は重要なポイントです。

コンテンツマーケティングの運用に求められることは、大きく2つあります。それは「良質なコンテンツをつくること」と、「SEOの正しい知識・技術」です。複数メンバーを用意する際は、この2点を意識して適任を探すのが良いでしょう。前者であれば、WEBライティング能力に長けた人材であり、後者であればSEOスキルが高い人材となります。両方に精通している人物であれば、SEOを意識したライティングができるので理想です。
1-6. 経験者をチームに入れなかった
自らの学習期間も含めて考え、長期間を想定してコンテンツマーケティングにチャレンジする場合は良いですが、そうでない場合はコンテンツマーケティング経験者、あるいはWEBサイト・ブログ運営の経験がある人材を用意するのが望ましいでしょう。
WEBライティング能力もSEOスキルも、学習によって向上させることができます。しかし「今、何をすべきか?」といったフェーズによって変わる課題は、経験者でないと判断がつかない部分もあります。仮にメンバーとして選任できないとしても、可能であれば相談役としてチームに迎え入れることができると、大きなプラスになります。
経験者がいない状態で開始し、期待値を大きく下回ったことで更新をやめてしまうケースは、せっかく蓄積したコンテンツや割いたリソースが水の泡になってしまう失敗事例です。
1-7. 短期間で効果がでると思ってしまった
「コンテンツマーケティングとは?メリット5点+デメリット3点」でも書きましたが、コンテンツマーケティングは短期間で効果が出るマーケティング手法ではありません。むしろ開始してから数ヶ月、効果がほとんど見えなくても継続する覚悟が必要です。

この点の認識が甘いと、運営をはじめてから効果を求めすぎてしまったり、なかなか思うようにいかないと諦めたり焦ったりしてしまいます。よほどの拡散力が無い限り、検索エンジンから評価されるには時間がかかるので、立ち上げ当初はぐっと辛抱する期間も必要です。
想定とのギャップを感じるだけなら良いですが、運用途中で良い兆しが見えるにも関わらずコンテンツの更新を怠ったり、中止してしまうようなことは避けるべきです。
1-8. 「注力すべきこと」を見誤ってしまった
コンテンツマーケティングに限った話ではありませんが、注力すべきことにリソースを割けないことは、失敗事例を作り出す要因となります。
コンテンツマーケティング開始当初は、あれもこれもと時間を使ってしまいがちです。Facebookのファンページを作ればファン数が気になるし、Twitterのフォロワーも気になります。特にTwitterは気をとられやすく、かつツイートも手軽にできるので、気がつくとずいぶんと時間を使ってしまうことも。

しかし限られたリソースでコンテンツマーケティングを運用するには、注力すべきことを見誤らず、一つのことにリソースを集中投下すべきです。では数ある選択肢から何を捨てて、何に注力すべきでしょうか?
筆者は、良質なコンテンツづくりにリソースを集中投下すべきだと考えます。読者にとって、一番大切なことはコンテンツが良質である点です。コンテンツが良質であれば、固定読者がついてくるので、それからソーシャルメディアマーケティングに力を入れても遅くありません。むしろ開始直後よりも拡散力は高まっているので、比較的リソースをかけずにマーケティングができるでしょう。
2. オウンドメディア構築の失敗例
まずはオウンドメディア構築における失敗事例です。オウンドメディア構築と聞くと予算や工数がかかるイメージでしょうか?しかし実際はスモールスタートする選択肢もあります。その場合は、必ずしも予算や工数が大きくかかることはありません。その点を意識しながら、失敗事例をご確認ください。
2-1. サイト開発に予算をかけ過ぎてしまった
オウンドメディアをつくるのに、最初から予算をかけてWEBサイトを開発してしまうという失敗事例です。無論、そのまま軌道に乗った場合は問題ないのですが、Wordpressに代表されるCMSを使用することで予算を抑え、アクセスが集まる目処が立ってからデザインをリニューアルする選択肢もあります。

複数オウンドメディア運用の経験者でもない限り、成功する可能性は未知数です。なるべく初期投資を抑えて、状況を見ながらサイトを改善していく方法を推奨します。
2-2. SEO対策ができていないWordpressテーマを選んでしまった
WordPressを使用してオウンドメディアを構築する場合に限りますが、Worepressテーマの選定は重要です。どのテーマが適しているかは、扱うトピックやターゲットなど複数の要素によりますが、必ずSEO対策がされているテーマを選びましょう。
すくなくとも「wordpressテーマ seo対策」といったキーワードで検索して、情報収集をしっかりする。あるいはWordpressの知見がある方にアドバイスをもらうというのも手です。おそらくSEO対策ができているWordpressの定番テーマを知っているでしょう。
最近はデザインが秀逸なWordpressテーマが多いので、ともするとデザインに目がいきがちです。しかしSEO対策という目に見えない要素こそ、アクセスに大きく影響します。デザインだけでテーマを選ぶと、のちのちSEOに弱いことが判明して変更を余儀なくされる、といった失敗事例は過去に経験があります。
2-3. レスポンシブ対応していないWordpressテーマを選んでしまった
同様にWordpressテーマの選定における失敗事例ですが、テーマ選定の際は必ずレスポンシブ対応しているかを確認しましょう。Googleのモバイルフレンドリーアップデートの発表は記憶に新しいですが、今後もスマホ利用者は右肩上がりに増えていく予見があります。

もしオウンドメディアの運営を開始している方で、レスポンシブ対応か、せめてモバイル対応しているWordpressテーマを選定していない場合は、変更することを推奨します。
2-4. 環境構築に時間がかかってしまった
WEBサイトの環境構築は情報収集しながら進めると膨大な時間がかかります。例えば筆者はサーバー開設に関するお問い合わせを受けたことが多々あります。予備知識が無い中、レンタルサーバーかVPSか?プランはどれにすれば良いか?など、迷うポイントがいくつもあるので初心者が1人で進めるには難しい部分です。
環境構築に時間をかけ、運営開始までに時間をロスすることは一つの失敗事例だと言えます。予算によりますが、オウンドメディア構築を委託できる会社もありますし、任せられる部分は任せることで自社のリソースを確保することも大切です。
2-5. ドメインを検討せずに決めてしまった
オウンドメディアをどのドメインで構築するかには、新規ドメインと既存ドメインの2種類の選択肢があります。(ここでの既存ドメインとは、すでにWEBサイトを運用しているドメインを指しています)
基本的には既存ドメインを使い、アクセスを集めたいWEBサイトの下の階層にオウンドメディアを構築するのが一般的ですが、例外もあります。それは、WEBサイトとオウンドメディアのテーマの親和性が著しく低い場合です。この場合は、新規ドメインを取得する選択肢もあります。
肝心ことは、オウンドメディアの開始前に、どのドメインで構築するかを良く検討することです。ドメインを検討せずに決めてしまうと、あとで後悔する可能性もあります。
3. SEO関連の失敗例
オウンドメディアを運営する場合、SEOを理解せずに成功することはまず無いでしょう。SEOに自信が無い場合は、必ずSEOに詳しいメンバーをアサインする必要があります。その点は大前提として、SEO関連のトピックでありがちな失敗事例をご紹介いたします。
3-1.入念な検討をせずにサイトタイトルを決めてしまった
実際、サイトタイトルを適当に決める人は少ないと思います。ただ入念な検討をせずに、語呂やキャッチーな響きだけを考えてサイトタイトルを考えてはなりません。
サイトタイトル候補が出揃ったら、必ず検索にかけましょう。競合サイトが同じ名前を使っていないか、過去にネガティブな意味で話題になったキーワードでないかなど、一通り確認する一手間が肝心です。SEOの観点から言っても、基本的にtitleタグの変更は推奨しませんが、やむをえず変更する場合は、改めて入念に検討してから変更しましょう。
3-2. 記事カテゴリを適当に決めてしまった
オウンドメディアの構築後、コンセプトを決めて一安心してしまい、記事のカテゴリ選定まで気が回らない失敗事例です。記事を書きながら決めればいいやと、最初にカテゴリを適当に決めてしまうと、あとで苦労します。
基本的にはカテゴリは運営開始時に固定して、あとから何度も変更することは避けましょう。もし変更する場合は、むやみに何度も変更せず、作業開始前によく考えることが大事です。もちろん、運用をつづける中で変更を余儀なくされることもあるので、あくまで理想は開始時にバシッと決定して変更しないことです。
3-3. 記事テーマの選定を軽視してしまった
オウンドメディアのコンセプトを明確にしたことで満足してしまい、各記事のテーマを選定せずに運用してしまう事例も失敗につながる可能性があります。
5W2Hを全ての記事に設定することは、限られたリソースでの運用を前提にすると不必要です。そこまで手が回らないのが実情でしょう。ただせめて「誰に?」「何を伝える?」の2つは記事作成前に明確にしたいところです。

ちなみに、このコンテンツマーケティング失敗事例の記事は、次のように「誰に?」「何を伝える?」を設定してから記事作成をしております。参考までに公開いたします。
「誰に?」→コンテンツマーケティング運用を検討している、あるいは運用開始直後のWEBマーケティング担当者。Wordpress・SEO・サーバー構築などは詳しくない。
「何を伝える?」→コンテンツマーケティング運用にあたり、知っておくべき失敗事例。失敗のポイントを知ることで、先手を打つことができるようにする。※筆者はこの内容以外に、別途、細かく詳細内容を用意してから執筆しています。
3-4. パーマリンクの設定をしなかった
パーマリンクの設定方法については諸説ありますが、必ず開始前に決定することが大事です。何も設定せずに開始して、あとからパーマリンクを変更しようとするケースは、失敗事例の1つだと言えます。
なぜなら、あとから修正すると検索順位に影響する場合があり、かつ旧URLからのリダイレクト設定する必要があるので手がかかります。もし初心者の方が変更する場合は、SEOの知見がある方にサポートしてもらい、焦って自分で変更しないようにしましょう。パーマリンクの変更は、そう気軽にできる変更ではありません。(Wordpressでオウンドメディアの構築をされる方は、パーマリンク設定について下記の記事が参考になります。)
※参考記事
「WordPressのパーマリンク設定を変更して、SEOや日本語URLの対策をしよう」(LIGブログ)
3-5. SEOの知識が無く、学習時間もとれない状況で運用開始してしまった
オウンドメディア運営においてSEOの知識・技術は必須です。良質なコンテンツづくりにくわえ、SEOの知識・技術を高めることで、より自身が描く理想のオウンドメディアをつくることができるでしょう。
無論、SEOの知識が無いことを失敗事例だとは言いません。学習スピードが早い方であれば、数ヶ月の学習でだんだんとコツが掴めてくるはずです。むしろ失敗事例になるケースは、オウンドメディアの運営者がSEO初心者で、かつ何らかの事情でSEOの学習に時間を割けない場合です。
SEOはオウンドメディアの運営において非常に重要な要素です。もしSEOの学習時間がとれない状況であれば、知識や経験がある人材をあらかじめ用意することを推奨します。
最後に|失敗の積み重ねの先に成功がある
今回はコンテンツマーケティングにおける、ありがちな失敗18選をお伝えしました。おそらく、そんな失敗はしないと思う簡易なものから、経験しないとイメージができない難しいものまで、様々あったことでしょう。実は18選には入らなかった失敗事例も多々あります。ここでお伝えできなかったものは、また別途ノウハウとして何らかの形でお伝えできればと考えております。
しかし今回「失敗」という言葉を繰り返しましたが、コンテンツマーケティングにおいても失敗がないと成功はありません。
エジソンは1万回の失敗を、「うまく行かない方法を1万通り発見した」と言いかえて、失敗を前向きにとらえ、成功まで漕ぎつけました。コンテンツマーケティングも同様です。失敗事例を知り、学び、失敗を積み重ねた先に成功があるはずです。
CONTACT
コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。
また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。