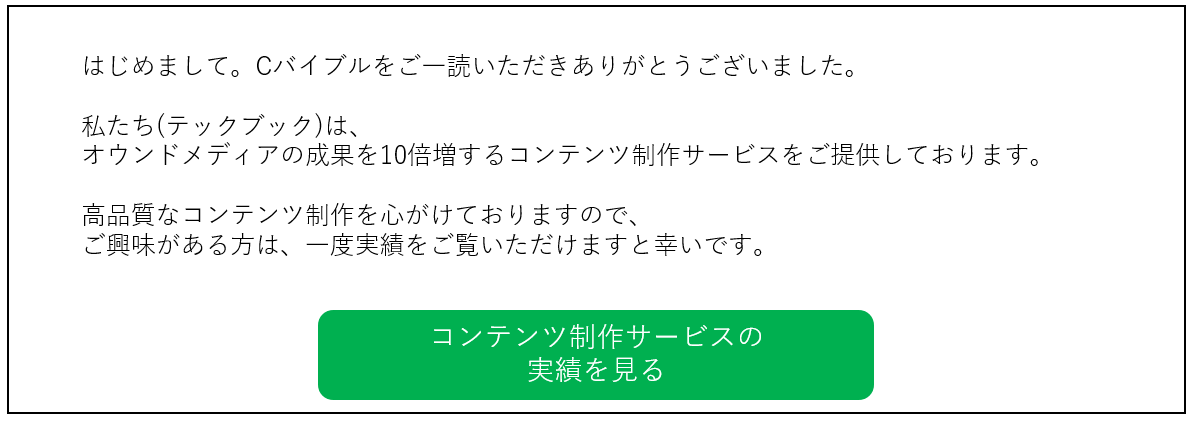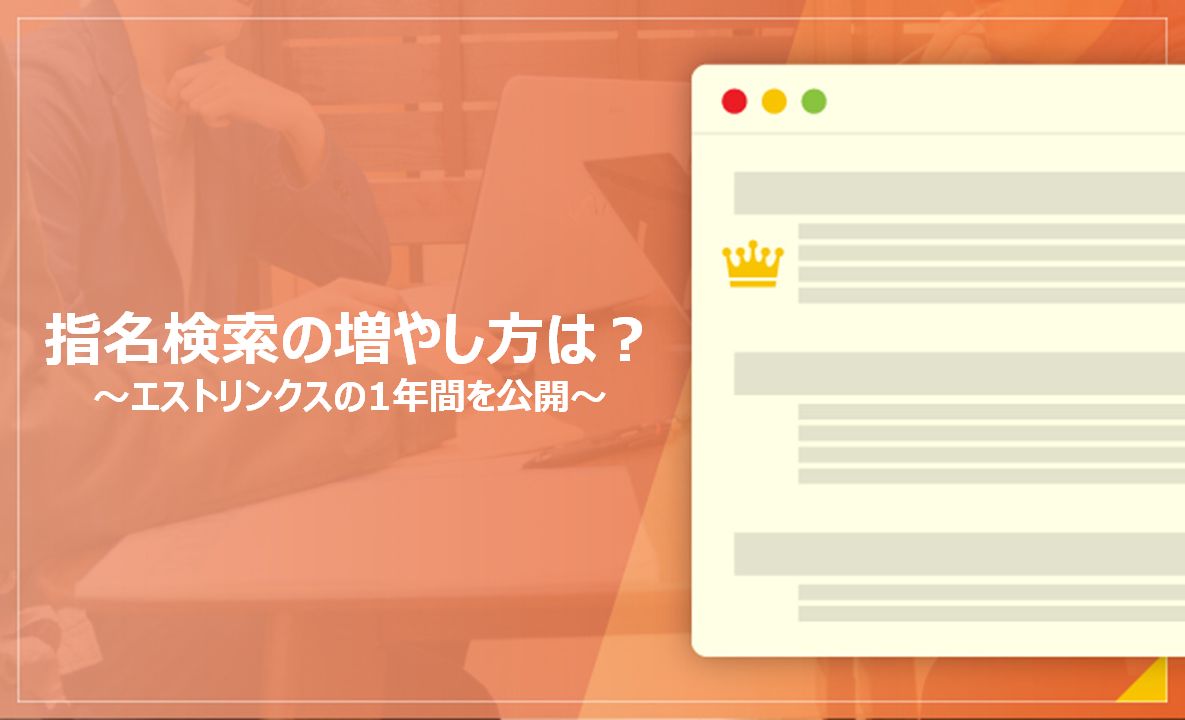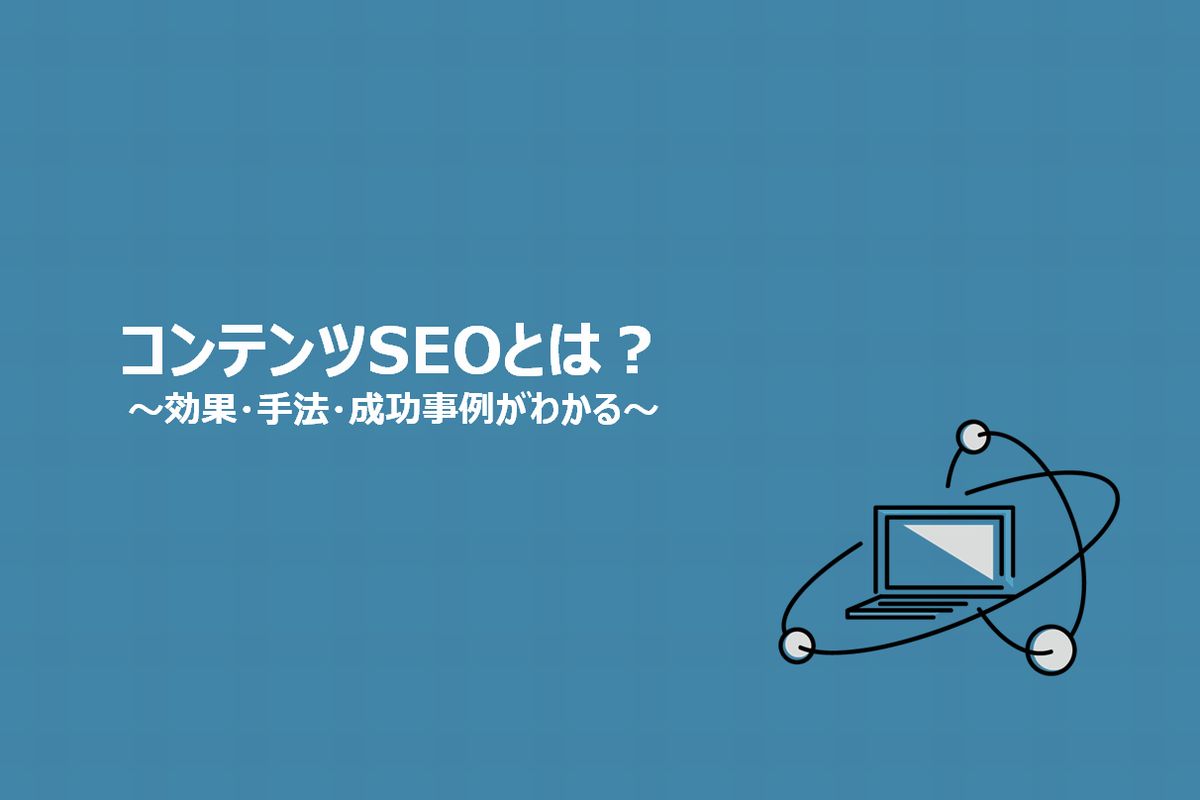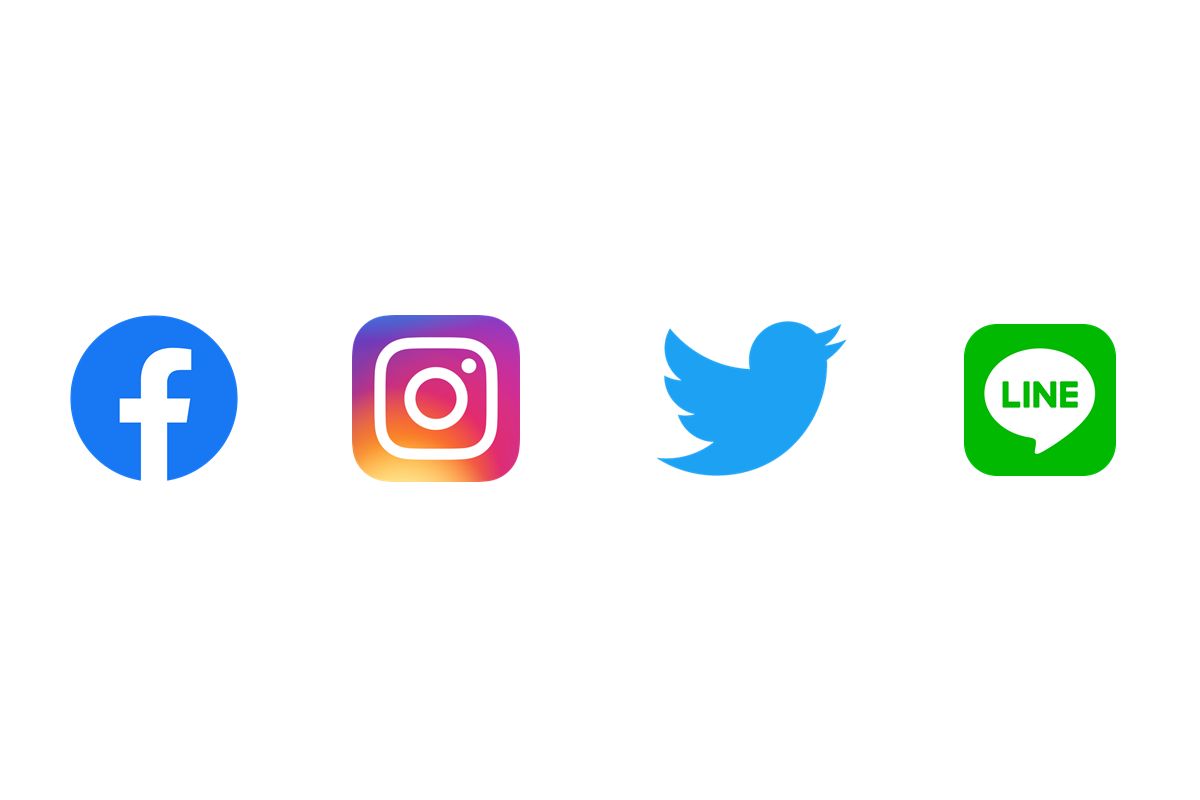「トリプルメディア」を一度でも耳にしたことがある方は、WEBマーケティングにお詳しい方かもしれません。
最近WEBマーケティングの担当者になった方、勉強をはじめた方は初耳かと思います。今回はトリプルメディアの解説と、2009年に定義されたトリプルメディアは古いアイディアか?といったことを検証していきます。
WEBマーケティング戦略において、どのメディアチャネルにどのようなコンテンツを投稿すればよいのか?オウンドメディアを運営する企業様やWEBマーケッターの皆様は、常に頭を悩ませていることでしょう。
トリプルメディアを知ることで、その考えを整理したり、戦略を俯瞰して見るためのヒントになれば幸いです。
そして最後に2015年のコンテンツマーケティングを再考しますので、WEBマーケティングの知見をいっそう深めていきたいと思います。
Contents
1. トリプルメディアとは何か?
トリプルメディアとは、企業がWEBマーケティング戦略を展開するための3つのメディアを指しています。それぞれペイドメディア・オウンドメディア・アーンドメディアと呼ばれています。

ちなみにトリプルメディアは2009年にアメリカで定義され、2010年に日本でも広く使われるようになりました。以前ソーシャルメディアの起こりを記事にしましたが、2010年はInstagramが誕生した時期でもあります。
ただFacebookの誕生は2004年ですので、2009年にはソーシャルメディアがすでに世界中に広がっていることがわかります。それでは、それぞれの用語の意味を見ていきましょう。
1-1. トリプルメディア①ーペイドメディアとは?
ペイド(paid)は英語で『支払った』ことを意味し、主にWEB広告がペイドメディアにあたります。特に『新規顧客の獲得』の際にペイドメディア(WEB広告)を使います。また、ブランディング志向が強いWEB広告であれば、顧客の関心を得るために使います。
潜在顧客にも顕在顧客にもリーチできますし、出稿量やフリークエンシーを調整することで、リーチの質を変えることもできます。ただ支払いが前提である点は、オウンドメディア・アーンドメディアと異なる点です。
1-2. トリプルメディア②ーオウンドメディアとは?
オウンド(owned)は英語で『所有している』ことを意味します。つまり、自社で所有しているメディアのことを指しています。広義の意味では、WEBサイトやランディングページ、メールマガジンも入りますが、近年では自社で保有する、ブログをはじめとするメディアを指す場合が多いです。
例えばWordpressではじめる場合など、必ずしも支払いが前提ではない点がペイドメディアとは異なります。またコンテンツが更新されるのは自社が保有しているメディアなので、万が一の有事の際も、比較的コントロールがききやすい点は特徴だと言えます。
オウンドメディアはペイドメディアのように、短期間での顧客獲得には向いていませんが、長期的に顧客との関係性を構築する際に有用です。
1-3. トリプルメディア③ーアーンドメディアとは?
アーンド(earned)は英語で『獲得した・得た』といった意味ですが、獲得する対象は主に顧客からの支持・共感・信頼を指しています。ただ難しく考えずに、アーンドメディア=ソーシャルメディア、口コミサイト(に代表されるCGMメディア)と捉えてしまって問題ありません。
特徴は、顧客と双方向でコミュニケーションがとれる点です。オウンドメディアも設計によっては可能ですが、双方向のコミュニケーションで商品・サービスのファンをつくることは、アーンドメディアが得意とする領域です。
実はトリプルメディアが定義された背景には、ソーシャルメディアの急成長があります。それまではお金を支払わないと企業は顧客にリーチすることが難しかったものの、ソーシャルメディアのユーザーが増えたことで無料でのプロモーションが広く普及していきました。
2. コンテンツマーケティングとは何か?
Cバイブルでも何度も出てくるコンテンツマーケティングという用語。今一度、ここで用語の意味を整理したいと思います。コンテンツマーケティングとは、なんでしょうか?
言葉通りに述べると「コンテンツを使ったマーケティング手法」ですが、コンテンツも様々です。例えば皆様が読むこの記事もコンテンツですし、他には動画や画像、インフォグラフィック、電子書籍などもコンテンツに該当します。それに広義の意味でのコンテンツは、WEB上にとどまりません。

コンテンツマーケティングにおいて大事なことは、アイディアの中心にある志向性にあります。それは「顧客にとって価値がある情報(コンテンツ)を提供すること」です。言うまでもなく、顧客が望まないコンテンツを大量生産してSEOをかける行為は、コンテンツマーケティングとは呼びません。
「コンテンツマーケティング戦略とは?」でも書きましたが、こうしたマーケティング手法が注目されてきた背景には、ペイドメディアでの顧客獲得が難しくなった現状があります。情報過多の時代においてWEB広告のCTR・CVRが下がり続け、業界全体でCPAが高騰してしまったのです。
その結果、低予算ではじめられ、かつ顧客との関係構築に向くコンテンツマーケティングが注目を集めてきました。
※参考記事
「コンテンツマーケティング事例厳選11選|ECサイト限定」
「注目ベンチャーの秀逸オウンドメディア事例9選」
3. トリプルメディアとコンテンツマーケティングの関係性とは?
良くいただく質問で、トリプルメディアとコンテンツマーケティングは何が違うのか?といったものがあります。また、2つの用語の関係性についても同様に質問をいただくことがあります。
実は質問の答えは難しいものではなく、先に述べた通り、コンテンツマーケティングは「コンテンツを使ったマーケティング手法」です。そして、あくまでトリプルメディアメディアは「メディア」ですので、それが違いです。
そして、トリプルメディアはコンテンツマーケティングをする際の「コンテンツの配信先」です。これが両者の関係性を表す答えです。
4. 2015年、トリプルメディアは古いのか?
ここまでトリプルメディアの解説をしてきましたが、2009年に定義されたトリプルメディアは、2015年の今ではすでに古いのでしょうか?確かにペイドメディア・オウンドメディア・アーンドメディアといった、それぞれのメディアチャネルを定義づけて考える必要性は、以前より薄れています。

photo by mkhmarketing−flickr
例えばFacebookを例にとると、自社メディアのコンテンツを更新して(オウンドメディア)、ファンページで拡散して(アーンドメディア)、同じコンテンツをFacebook広告に出稿する(ペイドメディア)というように、1つのコンテンツをトリプルメディアすべてに使用するケースもあります。
また以前、無印良品のコンテンツマーケティングを参考事例として挙げました。オウンドメディアでありながらも、アーンドメディアであるFacebookへの遷移や、"いいね!"およびコメントがしやすい設計は、もはやオウンドメディアもアーンドメディアも1つのメディアに内包しています。

実はトリプルメディアは様々な形で整理され、2010年には「How To Define Shared Media On Facebook」というタイトルの記事において、3つのメディアが重なり合う部分がシェアードメディアと名づけられました。シェアードメディアは、コメントや質問、議論などはシェアされるメディアであるという定義づけです。
どうやらトリプルメディアの定義も、時が経つにつれて形を変えてきました。なので2009年に定義されたトリプルメディアを、そのまま2015年にもってきて古いか?と聞かれれば、それは古いと言わざるをえません。
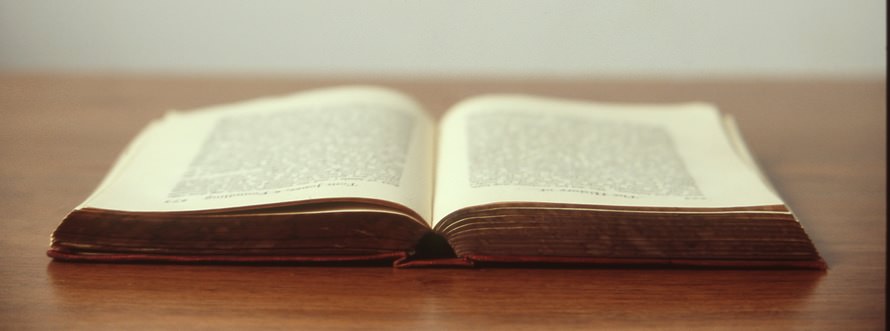
メディアチャネルの定義づけは、時代の変遷と共に様々な形で成されます。古いのか?という端的な質問には、古いと端的に返すしかありませんが、トリプルメディアのアイディアの本質は、決して古いとは言えません。
なぜならペイドメディア・オウンドメディア・アーンドメディアが担う役割、「新規顧客の獲得」「顧客との関係構築」「双方向のコミュニケーション」は、2015年も企業がそれぞれ戦略的に取り組むべき事柄だからです。
つまり、トリプルメディアを定義づける必要性が薄れても、各メディアが担う役割を理解して効率よくコンテンツを配信することは、2015年の今もなお求められるマーケティング戦略だと言えます。
5. まとめ|コンテンツマーケティングのゴールは?
コンテンツマーケティングにおいて本当に大事なことは、そのマーケティングを通じて実現するゴールを設定し、それを達成することです。
そして、そのためには「顧客にとって価値がある情報」=良質なコンテンツを制作しつづけることが重要です。なぜならメディアの役割を知り、戦略的にコンテンツの配信先を決めることができても、良質なコンテンツを制作しつづけることができなければ、ゴールは達成できないからです。
無論、良質なコンテンツの定義もあります。いくら「顧客にとって価値がある情報」を提供できていても、設定したゴールが集客であった場合、SEOが弱ければ良質なコンテンツとは言えません。顧客にとって良質であったとしても、企業にとっては集客につながらないので良質ではありません。
「顧客にとって価値がある情報」であり、「企業が設定したゴールを達成する」ことができる良質なコンテンツを制作しつづける。これはメディアの定義づけが変わっても、2015年も変わらない本質なのです。
以上、「トリプルメディアは古い?2015年のコンテンツマーケティングを考える」でした。今回も、ご一読ありがとうございました。またぜひCバイブルにいらしてください。
CONTACT
コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。
また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。