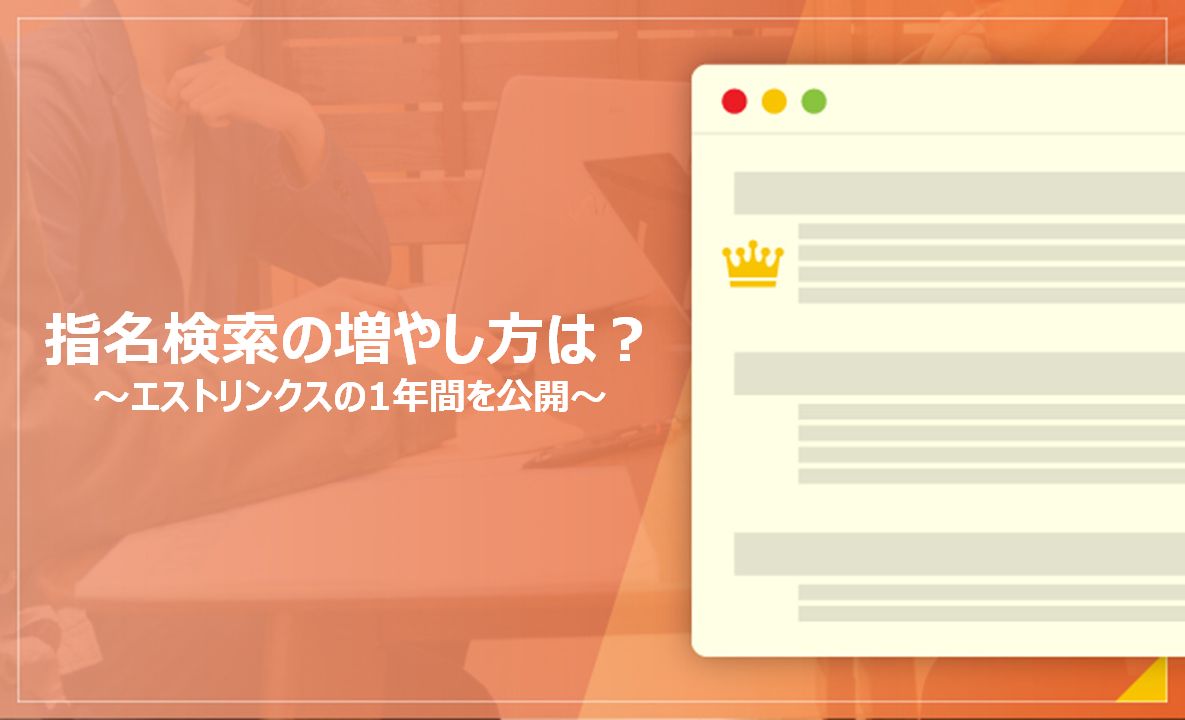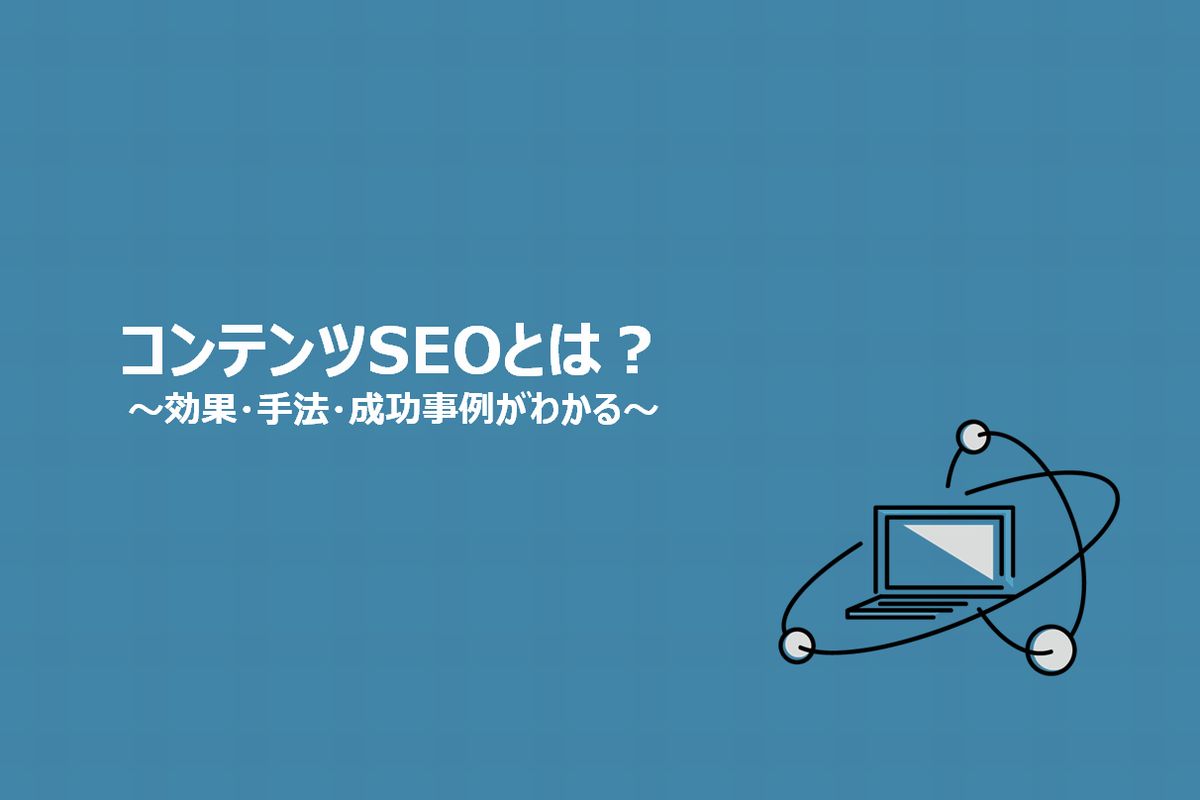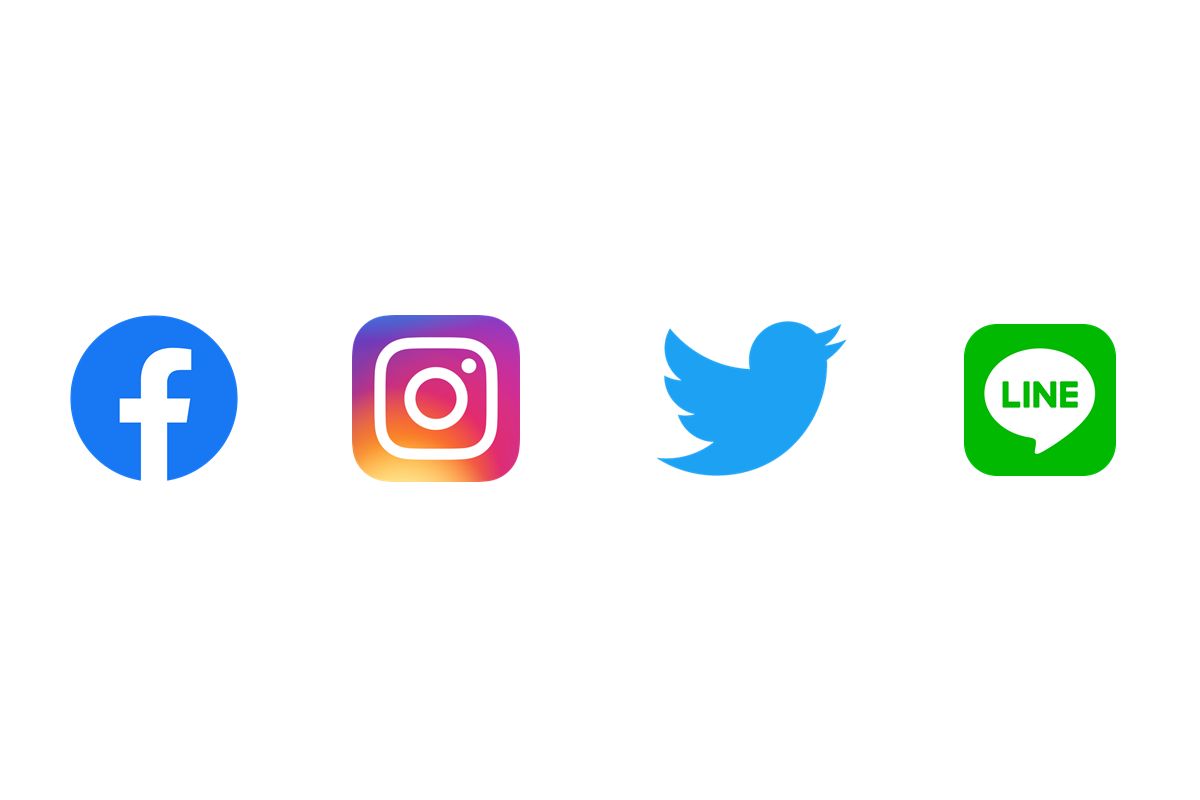美しい日本語とはどういったものでしょうか?
表現の幅が広がる一方で正しい日本語の使い方、日本語の持つ美しさ、その力が試されています。
若者言葉、横文字言葉の横行、二重敬語の慣用化等、日本語の使い方が多様化している昨今。
今回は日本が誇る文学作品から美しい日本語を探求してみようと思います。
「美しい日本語 表現」とインターネットで検索すると、もっとも多く名が上がるのが川端康成です。あの三島由紀夫も彼の文才に嫉妬したという逸話も残っています。
本棚にあるいくつかの川端康成の文学を読んで、各作品に共通することは、ストーリーの面白さではなく、思想の面白さでもなく、みずみずしいなにかがあります。非常に読みづらい文章ではありますが、とても魅力的な、自然と文章に引き込まれていく、そんな文章であるということです。
どこから読んでも、どこで終わっても面白い。起承転結以上に一つの文章が、また次の文章を読みたくさせる。ここに文章の本来の力が宿っていると思います。
川端康成はすべてのライターや文筆家の手本となるべき文章を数多く残しています。
それでは、川端康成の文学作品から5つの美しい日本語表現を技法ごとに紹介しましょう。
Contents
1. 「雪国」の詩的短文
『 国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。』
一般的には一文が長いほうがいいように思われますが、実は逆で文章は短ければ短いほうがよいのです。これは人が長い文章を記憶することは難しいためです。
有名な「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」という冒頭から始まる文章。わずか一行で情景が浮かんできます。ここからイメージされる情景は、暗くて長いトンネルを、汽車に揺られ、突然闇の世界から外へと抜けだし、一面に広がる銀世界。
さらに「夜の底が白くなった」という文章は、かなり新感覚派的な文章で、分かりにくく難解でありながらイメージは掴めます。この『雪国』は詩的ともいえるイメージの連鎖で紡がれています。
川端康成も「国境のトンネルを抜けると、窓の外の夜の底が白くなった。」を「国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。」と短くしています。こうすることで文章に美しさとリズムが生まれます。
2. 「雪国」の比喩表現
『駒子の唇は美しい蛭のやうに滑らかであつた』
もうひとつ「雪国」の中から。本作は多彩で美しい比喩が頻出します。豊かな比喩も日本文学の特色です。
比喩は「たとえ」の表現で、3種類あり、イメージをはっきりさせる効果があります。
1.直喩(または明喩)
類似性によって、明示的に、他のものごとになぞらえること。
「~のようだ」や「~みたいだ」などを使い、たとえるものとたとえられるものをはっきり示す。
例)僕の人生は旅のようだ。
2.隠喩(または暗喩)
類似性によって、他のものごとの名称を用いること。
たとえるものとたとえられるものをそれとなく示す。「~ようだ」などを使わない。
例) 僕にとって人生は旅だ。
3.擬人法
人でないものを人に見立てた表現。
例)秋の風がささやく。
川端康成はこの文章の中で「唇」を「美しい蛭のよう」と直喩しています。
「蛭」に例えて表現することで、唇の「柔らかさ」の他に、女性特有の「温度」や「危うさを」想像させます。ただ「唇が」というよりも、「蛭のよう」と直喩することで読者に具体的なイメージが与えられ、文章をより豊潤でリアルなものにすることができます。
直喩は、類似しているから用いられるとは限りません。むしろ、直喩を用いることによって、読者に対して類似性が提示されます。そもそも類似性がないものでも、読者に対して提示することで、それが記号として成立している現実が浮かび上がってきます。対象と似ているから表現が成り立つのではなく、表現によって対象の類似性が認識されることもあります。
3.「雨傘」の倒置技法
『写真屋へ来る道とはちがって、ふたりはきゅうに大人になり、夫婦のような気持ちで帰っていくのだった。 傘についてのただこれだけのことで ―。』
倒置法とは、語順をひっくり返す修辞法で、言葉を美しく巧みに使って、効果の高い表現をする手法です。「倒置法」は、伝えたいことを強調するためなどに使われます。この場合、後ろに来た文が強調されます。
倒置法でなく普通に書くと
『傘についてのただこれだけのことで、写真屋へ来る道とはちがって、ふたりはきゅうに大人になり、夫婦のような気持ちで帰っていくのだった。』
倒置法の効果には、次のようなものがあります。
・倒置により後ろに来た文の印象を強める
・意外性をねらう
・感情の変化をありのままに表現する
・文のリズムに変化をつける
あまり多用しすぎると強調の意味が薄まってしまい効果が弱まり、さらに不自然な文章になってしまうことに注意して使いたいですね。
「雨傘」では、傘の中でお互いに意識をしすぎて体を近づけることのできない少年少女の、初々しい情景と体と心の距離が、ただ傘をさすという行為だけのことで縮まっていくシーンを印象的かつ感情的にも美しく書かれています。ただ、傘についてのただこれだけのことで。
4.「山の音」の対義結合
『月の夜が深いように思われる。深さが横向けに遠くへ感じられるのだ。』
対義結合は、矛盾する言葉や相反する言葉を結びつけて新たな意味を生みだす技法です。とくに、反対の意味をもつことばを結びつけるのがその典型です。
この場合、深いといえば闇夜なのに、月夜が深いという不思議な表現で書かれています。少し月明かりがあるほうが、かえって夜の深さが感じられるということかと思います。実に美しい、常識に逆らって伝える技法です。
松尾芭蕉の「閑かさや岩にしみ入る蝉の声」もこの技法が使われています。蝉が鳴けばうるさいはずなのに、かえって閑かさが感じられると言っています。
また、深さといえば鉛直方向なのに、それが横向けに遠くへ感じられるというのも、この技法の妙です。いわば「縦のものを横にして」伝えています。闇夜だったら、横の広がりも分からないはずです。しかし月夜ならば、横方向の遠さに気付いて、かえって夜の深さが身にしみてくるということでしょう。
矛盾した言葉づかいが使われることになるので、その意味を簡単には理解することはできません。このことから、単純ではない深い意味あいを持たせることができます。また時には、その中に一種の「真理」を含ませようとすることもできます。
「山の音」では、誰かの面影を追う主人公の複雑な感情をこのような文章技法を持って表現しています。歳を重ねるにつれて、どうしても解決できないものへのモヤモヤが山の風景や音を感じることを、対義結合を通してうまく書かれています。
5.「伊豆の踊子」の色彩効果
『道がつづら折りになって、いよいよ天城峠が近づいたと思うころ、雨足が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓からわたしを追って来た。』
文章に色彩表現を入れることで視覚は限定されず、むしろ情景は多角的にイメージしやすくなります。
導入にふさわしい書き出しで、あたりの情景と自分の感情が入り交じり、今後の展開をほのめかすかのような書き出しになっています。書き出しはこうありたいものだという教科書的な書き出しです。
つづら折りという単語のイメージが大山を匂わせ、杉、雨の白という色彩のイメージ、そして山特有の天候の変化。短いながらもその全てが含まれて、伊豆の山中の情景が行ったことがなくても何となく浮かんできます。
「雪国」と同じく『白』という色彩表現を入れることで色を限定化してイメージしやすくなっています。しかし、この白は雪の白ではなく、雨の、もしくは霧のような、眺望的な白であることがイメージできます。
まとめ|自然な文章の中に美しい日本語の表現技法を
今回は、川端康成の文章を例に挙げて、修辞法や情景描写といった日本語の美しい表現技法を紹介しました。
普段何気なく読んでいる文章の中にも、こんなにもたくさんのレトリックが含まれています。語順の入れ替えや表現が自由な日本語だからこそ、たくさんの文章と文学が作り出され、文学作品の数は日本が世界一を誇るまでになりました。
思いつくままの文章に、さらにこのような技法をちりばめて魅力的な文章にしましょう。美しい日本語を使いこなして文学への楽しみを増やしていきましょう。
今回紹介した表現やその技法が、みなさんのライティングのお役にたてばなによりです。
CONTACT
コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。
また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。