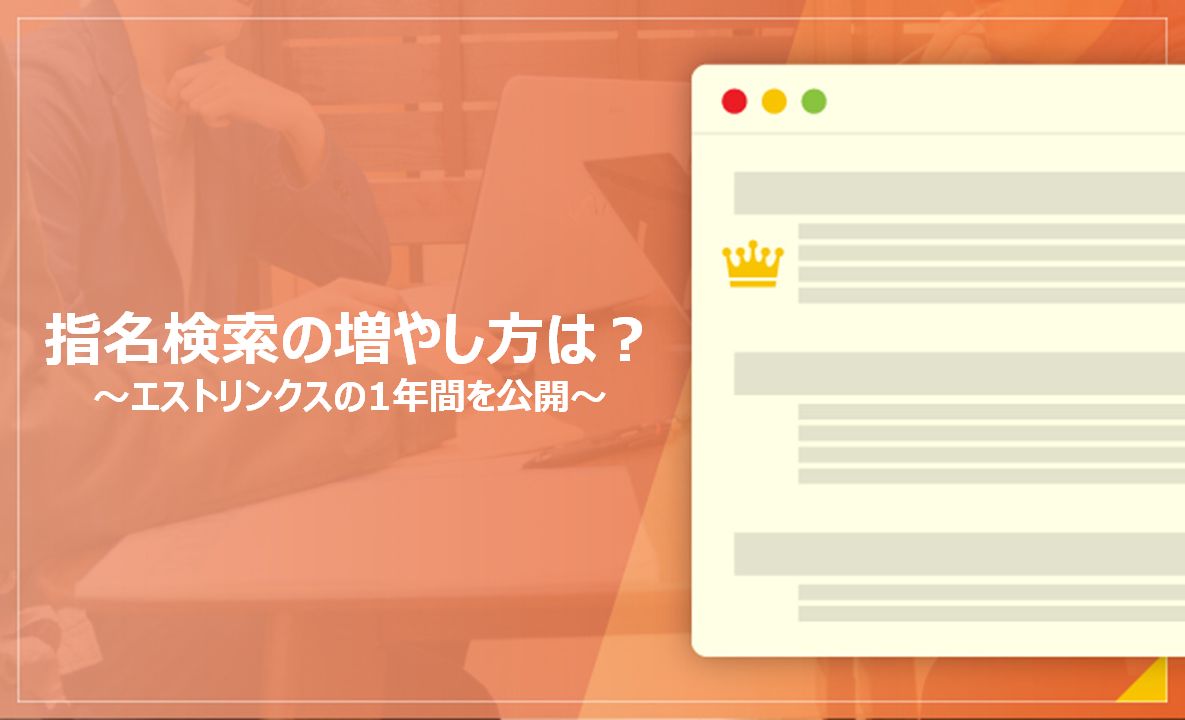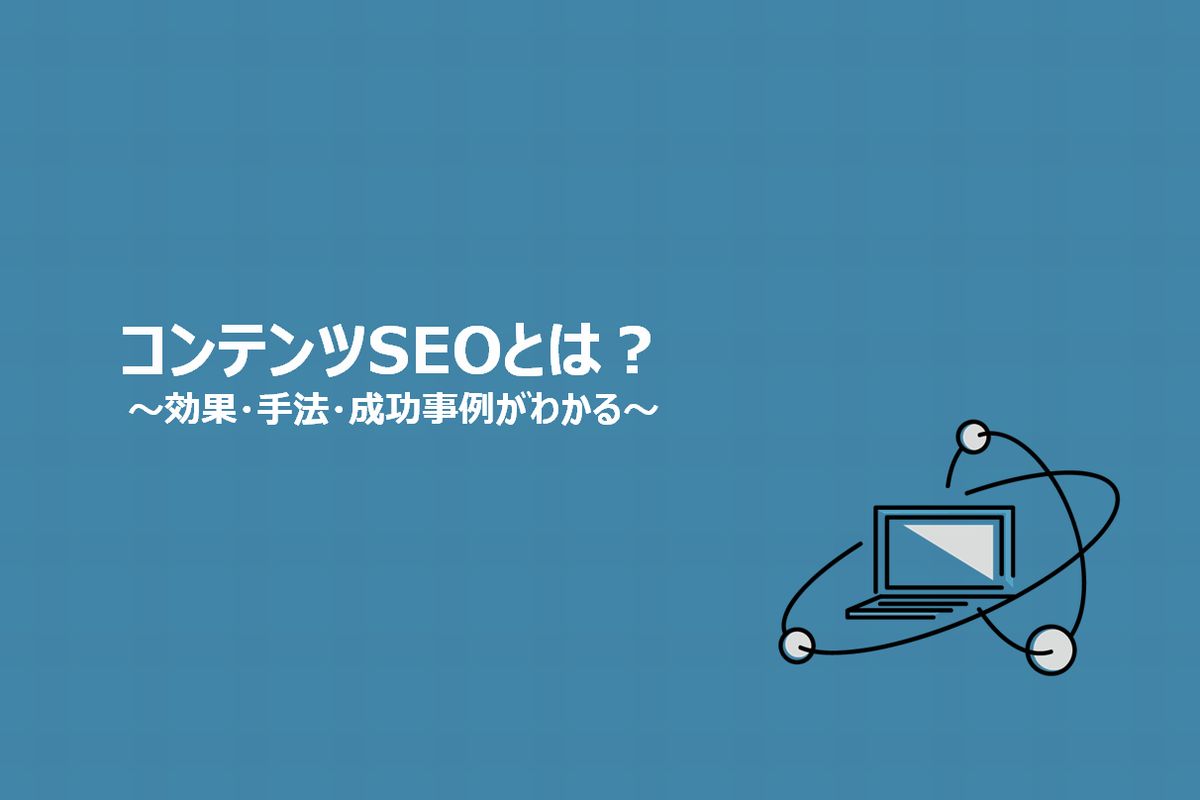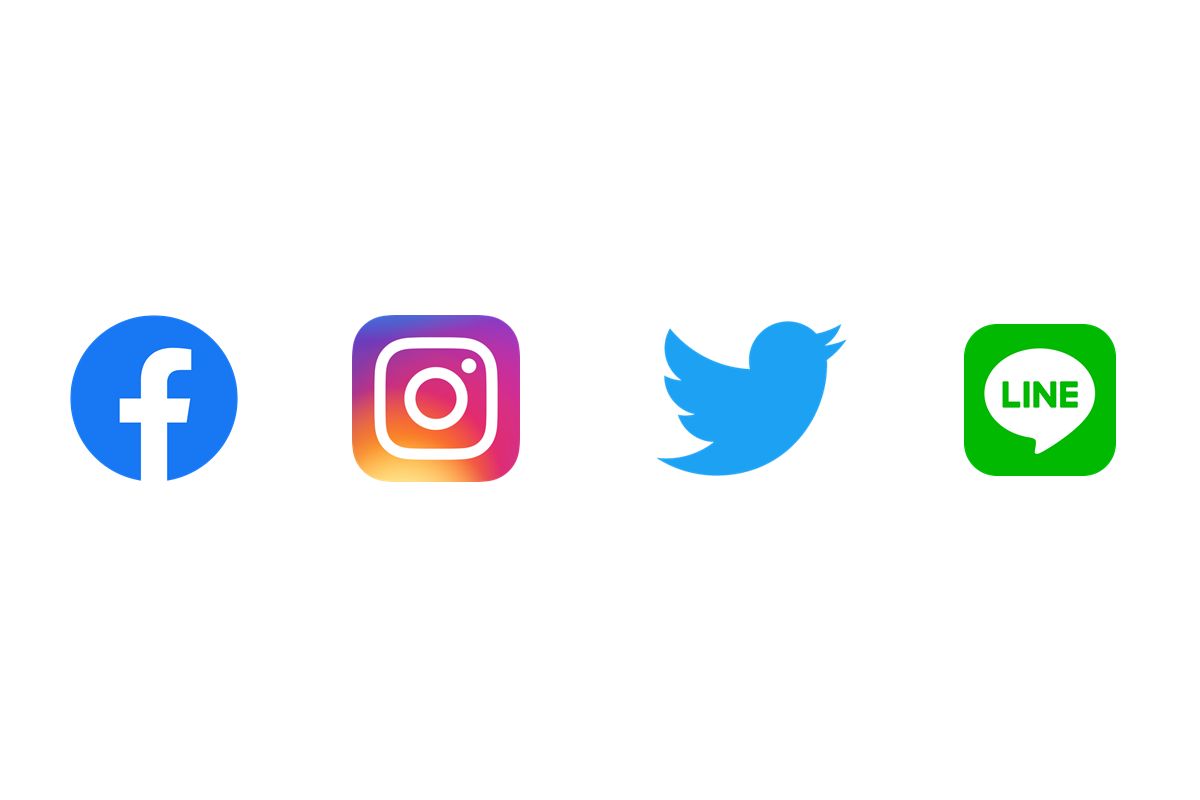株式会社エストリンクス代表取締役。2012年、htmlコーダーや業界紙の新聞記者を経てWEBライティング専門の記事作成代行・エストリンクスを創業。クラウドワークス様でのウェビナーなど、SEOやコンテンツマーケティングに関する講演実績多数の上級ウェブ解析士。
周りから「SEOやWEBマーケティングのおすすめ資格は?」「ウェブ解析士って取得してどう?」と時々質問されることがあります。ウェブ解析士の資格は万能ではありませんが、(個人的には)取得してよかったと思うポイントが多いため、「ウェブ解析士の資格は持っていないよりは持っていたほうがいいよ」とお伝えしています。自分が資格を取得してよかったポイントが多かったからです。
今回は、ウェブ解析士の概要や難易度、実際に受験・合格した感想を書きます。
こんな内容について紹介します。
自分の体験では、WEBデザイナー・ライターなどのクリエイター、広告代理店の営業担当の方がウェブ解析士を取得するのは大いにアリです。たとえば、企業への導入事例を見ると、博報堂さんが積極的に導入しています。また、いままで気ままにやっていたSEOアフィリエイターの方が資格取得すると、企業案件を受けやすくなるだろうなと感じました。
Contents
ウェブ解析士とは?

ウェブ解析士とは、38,000人以上が受講したWEBマーケティングの体系的な知識・スキルを学べる資格です。一般社団法人ウェブ解析士が運営し、資格を発行しています。
ウェブ解析士・上級ウェブ解析士・ウェブ解析士マスターという3つの段階があり、それぞれ難易度が異なります。
僕は実務経験が先行していたので、上級ウェブ解析士までは割とスムーズに合格しました。『下請け案件7割のウェブ制作会社が1年で56%を直取引にできた理由』という記事も書かせてもらっています。
ウェブ解析士の学習内容
ウェブ解析士試験の学習内容は以下の通りです。
|
第1章 |
ウェブ解析と基本的な指標 |
解析の意義や基本的な指標、基本的なマインドについて学ぶ |
|
第2章 |
環境分析とマーケティング解析 |
環境分析(ユーザー分析・市場分析・競合分析・自社分析)と新製品やサービスの展開方法を学ぶ |
|
第3章 |
デジタル化戦略と計画立案 |
事業戦略に基づいたデジタル化戦略の展開方法と、KPI策定・計画立案を学ぶ |
|
第4章 |
ウェブ解析の設計 |
事業戦略から生まれた施策が計画通りに進むかを計測する、ツールの設置・設定などの解析環境の設計方法を学ぶ |
|
第5章 |
インプレッションの解析 |
WEBサイトへ訪問する前のユーザーにどれだけ露出されたか、最適化の方法を学ぶ |
|
第6章 |
エンゲージメントと間接効果 |
永続的な事業発展に必要なエンゲージメントと、広告成果・間接効果について学ぶ |
|
第7章 |
オウンドメディアの解析 |
オウンドメディアの効果を最大化させる解析手法と改善方法、収益化について学ぶ |
|
第8章 |
ウェブ解析士のレポーティング |
相手に伝わり、相手を動かすレポートの作り方を学ぶ |
ウェブ解析士はただレポートをまとめ、分析するスキルを学ぶだけではありません。「なぜWEBサイトを立ち上げ、運用するのか」といった視点で基本的な考え方を学びます。
もともとはWEBサイトの解析が中心だった経緯からか、SEOやGoogle Analyticsの話が目立ちます。ただ、現在ではSNSやアプリ領域も見逃せなくなったためカリキュラムに加えられているようです。ちなみに、「SEOって何?」という方は『SEOとは?初心者にわかりやすく対策方法と仕組みを説明』をご覧ください。
ウェブ解析士の学習の流れ
ウェブ解析士の学習・試験に合格するまでの流れを紹介します。
- 1.認定試験に申込
- 2.認定試験を実施(指定会場またはオンライン)
- 3.合否判定
- 4.合格の場合は2週間以内に認定レポートを作成
基本的には『ウェブ解析士認定試験公式テキスト』で学習範囲について学びます。公式から試験対策用の問題集もあるので活用しましょう。
ウェブ解析士マスターによる認定講座・Googleアナリティクス講座なども資格試験において有効です。「何から手をつけたらいいかわからない」という方なら受講してみるのもよいでしょう。
なお、Googleアナリティクス講座を受けておくと合格後のレポート提出が免除されます。僕は受講しませんでしたが、体系的に理解するなら申込してもよさそうです。
ウェブ解析士の難易度
ウェブ解析士の難易度について、2020年時点ですが、率直に言えば決して難しいとは感じませんでした。ただ、前提となる知識や職務経験に大きく左右されると思います。
2018年以前のウェブ解析士の合格率は60~70%程度を推移していました。2019年以降は公表されていません。
ウェブ解析士の試験内容は、在宅で60分以内に60問を4択問題の形式で実施します。基礎的な用語を覚えておけば質問内容が理解できるので、問題集をやっておけば対策もしやすいと思います。
試験合格後のレポートはGoogle Analyticsを操作しながら作成します。まったく触ったことがない人からすると難しいように感じるかもしれません。ただし、指示された内容に沿って操作すれば合格するので、基本操作を覚えることができたら十分です。
ただし、CPC(Cost Per Click=クリック単価)やCVR(Conversion Rate=問い合わせ率)など、3文字の英語が多いので、英語にアレルギーがあると大変かもしれません。
ちなみに、不合格の場合は再試験を受けます。再試験には費用がかかるので一発合格を目指しましょう。
上級ウェブ解析士やウェブ解析士マスターの難易度はもっと高いです。特に、マスターの難易度は1年がかりで受験するレベルらしく、かなり不合格・やり直しが出ていると聞きます。それだけ専門的な資格と言えますね。
参考記事:一般社団法人ウェブ解析士協会|ウェブ解析士の難易度や合格率はどれくらいですか?
ウェブ解析士を受験した動機
本来、僕は「クリエイティブ大好き!時間もお金も気にせずガンガンやりたい」というタイプです。デザイナーさんやライターさんなど、こういう方は多いのではないでしょうか?ただ、これだと施策の効果やKPIなど数値を求められたときに弱いですよね。そんなわけでウェブ解析士の試験を受けはじめ、2020年4月に上級ウェブ解析士に合格(合格通知は5月)しました。
上級ウェブ解析士合格しました!
— 安藤 悟@SEO/コンテンツマーケティング静岡No.1 (@ando3106) May 22, 2020
大変だったけどGoogle Analyticsに見慣れてきたりウェブ解析の基礎知識みたいなことがあらためて学べたりしてよかった。
今度は実務で精進します…!
実務で2年程度レポート作成もするようになっていたので取得まで速かったのだと思います。また、短期集中タイプなのでひたすら勉強していました(笑)
ウェブ解析士に限りませんが、資格を持っているだけでは意味がありません。きちんとスキルを身に付けてお客様の成果に結びつけることが大切です。
一方でスキルがあるだけだとビジネスでは許されません。
たとえば、SEOをやるにしても「結果的に上位表示ができればいい」というだけではなく、施策の効果やゴールを説明する必要を感じるようになりました。
特に、静岡の会社さんからSEOを頼まれたときに、「サイト構造はこう考えましょう」「コンテンツってこうやって作るといいですよ」「リンクをこうやって集めるといいですよ」とお伝えすることは得意でしたが、費用対効果や施策ロジックの説明は苦手でした(実際に、順位が上がったので最終的に満足いただける例も多かったです)。
ただ、「コラムなんて書いて意味あるの?」「どんなコラムを書けばいいの?」とか、あるいは成果が見えない時期は「本当に意味あるの?」と指摘される機会も少なくなかったです(いまでも言われますが、数値の話ができるようになってからだいぶ減りました)。
自分でアフィリエイトをするだけなら、誰かに事細かな施策やロジックを説明する必要はありません。ただ、相手に説明するときはロジカルでなければ説得するのは難しいです。体系立てて人に説明したいなと感じるようになり、ウェブ解析士の試験勉強を受けることにしました。
コロナ以前は、「ホームページ制作ってできる?」という切り口からお話をいただいていて、SEOやSNSを使った集客があるよと話していました。ただ、「SEOやるメリットはあるの?」「オンラインで集客する意味って何?」と聞かれたときに悩んでしまうことも正直多かったです。
関連記事:地方の中小企業がSEOに取り組む意味ってあるの?メリット・費用対効果・怪しい電話営業の業者を見分けるコツ
ウェブ解析士の資格試験を受けた感想
結論から言うと、ウェブ解析士の資格を取得してよかったなと思い、上級ウェブ解析士まで取得しました。ただ、いいところや悪いところはあったのでレビューします。
ウェブ解析士の取得は万能ではありません。ウェブ解析士を受講すべきか迷っている人は、読んでいただけると参考になると思います。
ウェブ解析士を受験するメリット
ウェブ解析士を受講して感じたメリットは、
- 自信がつく
- 対外的な印象がよくなる
- コミュニティ内での交流
この3つです。ひとつずつメリットを紹介します。
自信がつく
ウェブ解析士の学習および試験では体系的にウェブ解析について学ぶため、WEBサイトや施策改善に対する考え方が変わり自信がつきます。
まず、どの指標を改善すると成果につながるかをイメージしやすくなりました。極端な話ですが、売上が2倍にしたいときにリスティング広告の単価を倍増する以外の発想が生まれます。たとえば、サイトのCVR(コンバージョン率)やクリック広告のCTR(クリック率)の改善など、抜け漏れなく考えられるようになりました。
次に、ウェブ解析士の試験ではSEOやリスティング広告だけでなく、SNSやアプリの解析についても学びます。普段は使わない指標も多くて新鮮です。
アプリは自社の事業には直接関係ない領域でしたが、お客様とアプリ開発の話が出たときにお伝えできる話が増えたときによい点だと感じました。WEBに関する相談を幅広く受けられるのは自信になります。
対外的な印象がよくなる
ウェブ解析士、特に上級ウェブ解析士の資格を持つようになってからお客様からの反応もよいです。
お客様とお話したときにウェブ解析士の資格があると、それなりに信頼してもらえます。実務経験や実績ありきだと思いますが、対外的にスキルを証明しやすくなったと感じます。
これまで自分は「野良SEOアフィリエイター」だと思っていました。とにかくいいコンテンツを作って、被リンクを獲得して、CVR改善すれば合格と考えていましたが、コンサルティングをするならそれだけでは説得力がありません。ウェブ解析士を受講したきっかけですが、体系的に理解し、説明できるようになったのがよかったポイントです。
「なぜ、その施策をするのか」「施策の費用対効果はどのくらいインパクトがあるのか」など、SEOや各種施策を打つべき理由を説明するきっかけづくりにもなったと思います。
コミュニティ内での交流
おそらく、ウェブ解析士のコミュニティへの所属に価値を感じている方も多いと思います。
ウェブ解析士同士で運営されるコミュニティやイベントが誕生し、ウェブ解析のムーブメントが起きているように感じました。僕はまだ少し参加している程度ですが、こういった取り組みもワクワクします。
ウェブ解析士同士でSEMRUSH(解析ツール)を解説するシリーズもあって、「いいなぁ」と思いました(個人的にはahrefsが好きです笑)。こんな感じでウェブ解析士のウェビナーなども開催されています。
また、資格をきっかけにウェブ解析のスペシャリストの方たちにお会いできて、実務上助かったというエピソードもあります。自社が不得意な分野のWEBサイト解析をお願いする機会もありました。これまでも解析分野について勉強してきましたが、頼れる方や尊敬できる方に出会えてよかったなという印象です。
ウェブ解析士のここが気になった
ウェブ解析士の試験を受けて資格を取得してみて、おそらくみなさんが気になるであろう点も少しありました。
まず、受験や資格維持に関する費用は決して安くない印象です。有料の関連講座を受けると試験時の免除や軽減などがありますが、逆に言うと、「講座を受けないと難しい」という側面もあります。更新費用も年間6,600円(税込)かかります。0からウェブ解析を学びたい人からすると、ひとつの高いハードルになるかもしれません。
また、結局は実務経験がモノを言う領域なので、「資格を取って即キャリアアップ」とか「ウェブ解析のプロと言えるか」というと微妙な気がします。覚えておいて損はない知識ですが、あくまで実践を助けるものだと考えると、期待外れにならずに済むと思います。
とは言え、費用面はWEBサイトやコミュニティ運営を考えるとやむないかなと感じました。個人的に受けてよかったと思っているし好きな団体なので、更新費などは前向きに考えています。実務経験者やマーケターの方が体系的に理解し、施策を立体的に理解する手助けだと考えると、期待外れに終わらず済むと思います。
まとめ
ウェブ解析士の資格は持っているだけだと役に立ちません。結局は事業に活かせないと意味がないので、「必要ない」という人がいるのは自然でしょう。
ただ、ウェブ系の制作会社や広告代理店の方が持っておくと、WEBマーケティングやコンサルティングの考え方が身につき、仕事がしやすくなります。自分の場合、資格取得後に「なぜ、自分の施策で成果が出たか?」を考えるようになったので、資格を受験してよかったなと感じました。
施策の効果を数値化する必要に迫られている方、あるいは自分たちの広告や制作物の効果を説明したいと考えている方は、ウェブ解析士の受験を検討してはいかがでしょうか?
自分はウェブ解析士の試験を受けてよかったなと思っています。資格試験を受ける方が増えても僕にお金が入るわけではありませんが、仲間が増えたら素直に嬉しいです。興味がある方はぜひどうぞ!
CONTACT
コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。
また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。