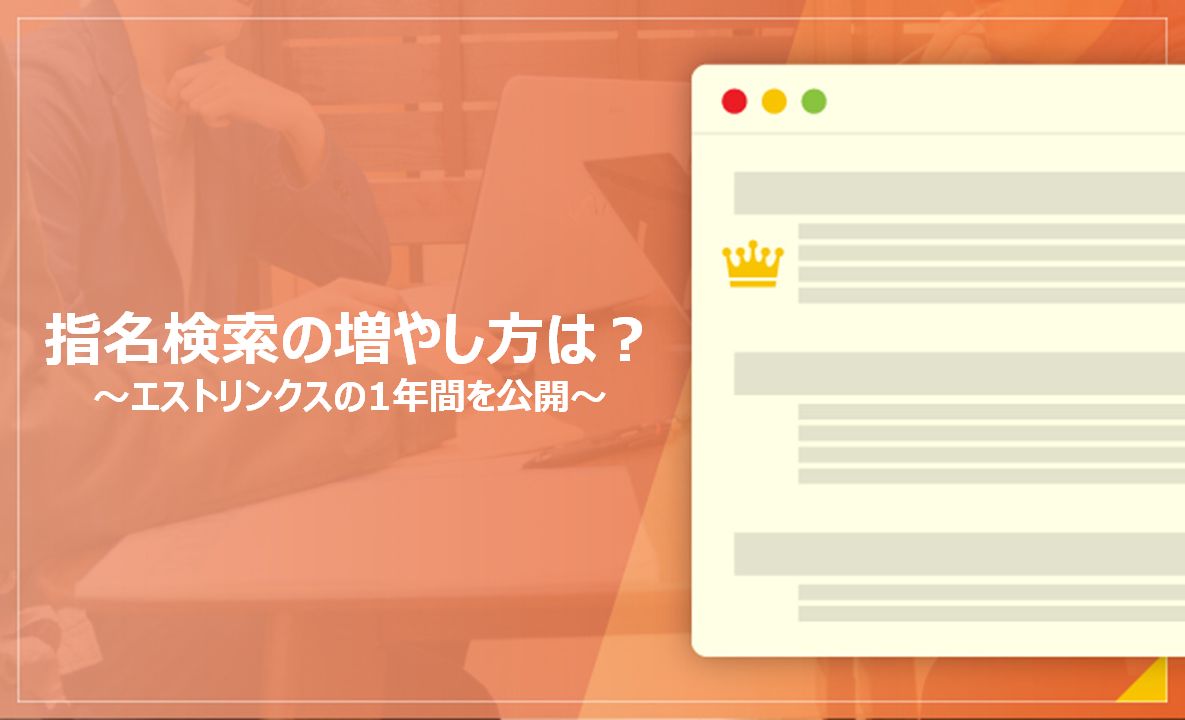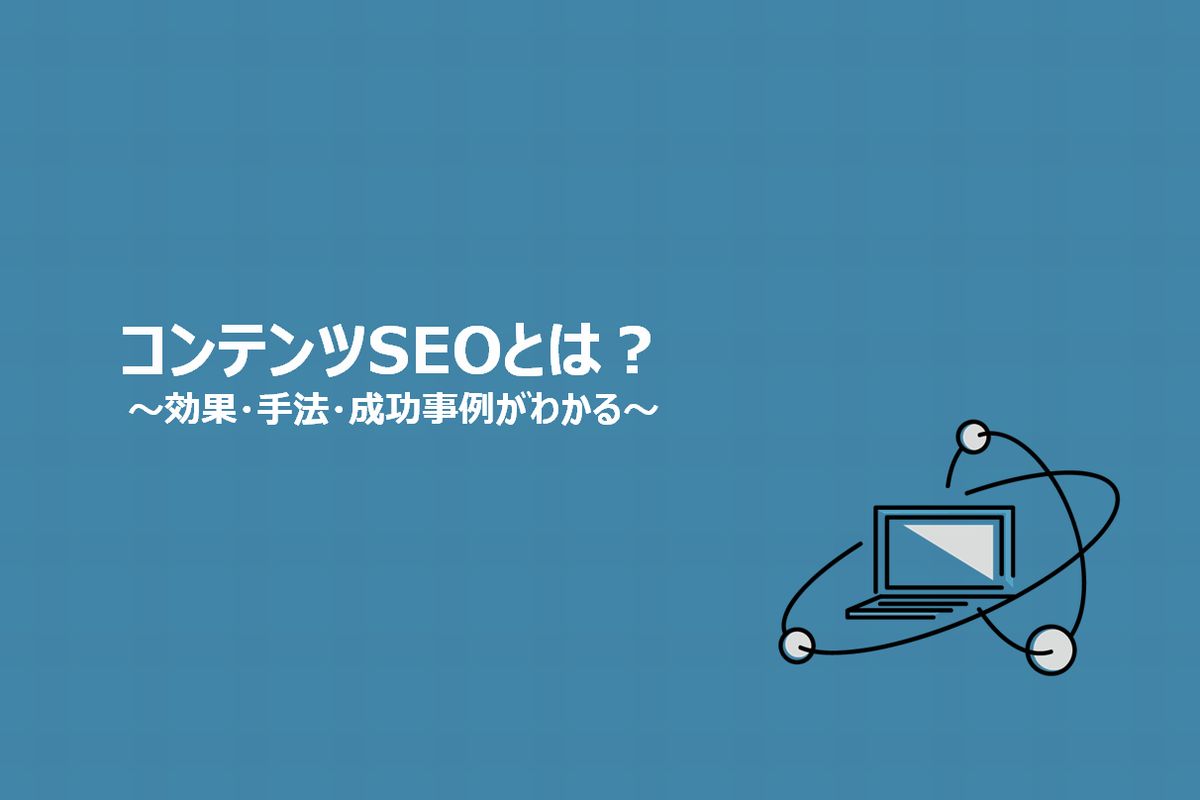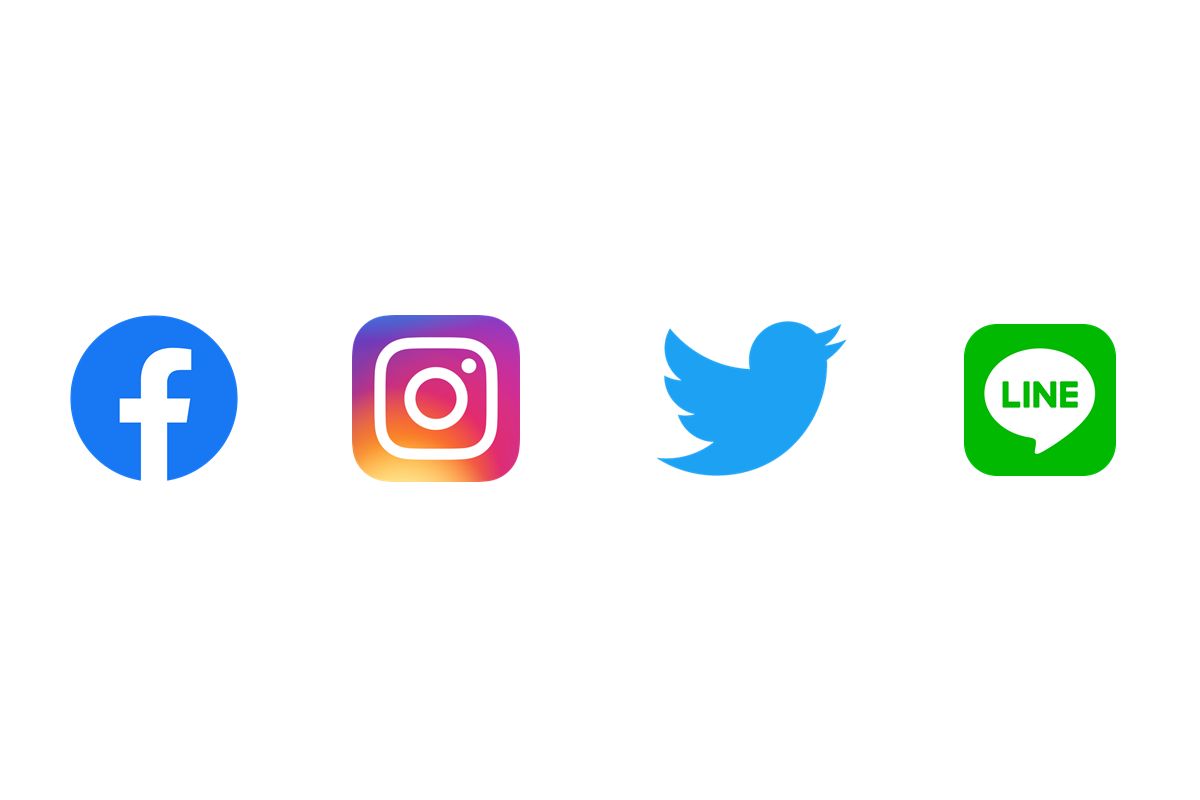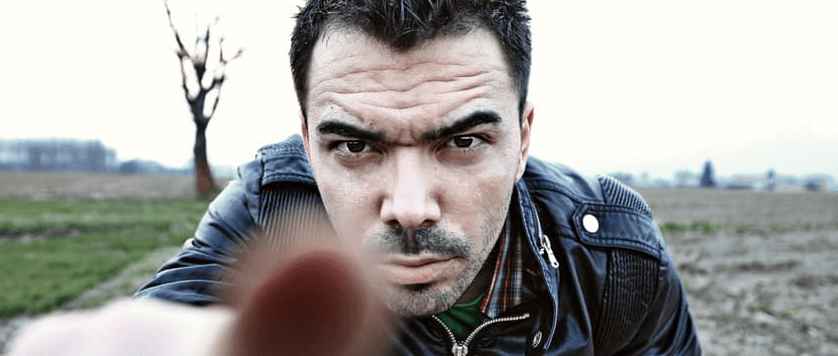
タッチポイントという言葉を聞いたことがありますか?
日本語だと「(顧客)接点」ですが、デジタルマーケティングではよくタッチポイントと言います。
カスタマージャーニーを作ったことがある方はわかるかと思いますが、どんな企業でも過去10年の変遷を辿ると、顧客とのタッチポイントが増えているはずです。
今回は、そんなタッチポイントに関する3つのTIPSを用意しました。B to Bであれば、リード顧客を増やしてリードナーチャリングに繋げたいですし、B to Cであればブランディングに繋げたいですよね?
まずは初めの一歩として、タッチポイントを理解していきましょう。
1.急増したタッチポイント
インターネットがこの世に存在しなかった時代、顧客との接点はオフラインでした。(当然ですね。)むしろ、オンライン・オフラインという言葉が存在しなかったはずです。
それから時が経ち、人々が何の疑いもなくインターネットに接続している今日この頃、タッチポイントはオンラインとオフラインの2つに分かれました。
そして、このオンラインでのタッチポイントは、年を追うごとに急増しました。理由の1つは、インターネット広告をはじめ、オンラインにおける顧客へのアプローチ方法が増えて、多様化したことが挙げられます。
今では、例えば「YouTubeで動画広告を観たあと、リスティング広告でランディングページを見て、後日ネイティブアドでコンテンツを読んでさらに気になった顧客が、そのブランドのオウンドメディアを読んだあと、商品ページに行って商品を購入する」といったストーリーも十分考えられるのです。

さらに今後、事業によっては、デジタルサイネージや店頭でのタッチポイントも考えてマーケティング戦略を考えるといった必要性が、どんどん高くなっていくでしょう。
2. タッチポイントを可視化すると理解できること
ここまで読んだ方の中には、「タッチポイントが増えたのはわかるけど、それが私たちのマーケティングにどう関係あるの?」と疑問をお持ちの方もいると思います。
しかし、タッチポイントが増えたことはデジタルマーケティング戦略を考える上で、大いに関係があるのです。なぜなら、タッチポイントが多いということは、それだけ顧客に影響を及ぼすアプローチの数が多いということです。
結果、どのアプローチがどのように良かったのか?といったことは、単純にラストクリックだけを見る効果測定ではわかりません。
現代において、タッチポイントを可視化して、各タッチポイントでどのような影響があったのかを理解する必要があるのです。その結果、私たちマーケターは各アプローチの本当の効果を理解することができるのです。
3. タッチポイントを繋いでストーリーを作る
先ほど、顧客とのタッチポイントが多い例に、以下のストーリーを挙げました。
「YouTubeで動画広告を観たあと、リスティング広告でランディングページを見て、後日ネイティブアドでコンテンツを読んでさらに気になった顧客が、そのブランドのオウンドメディアを読んだあと、商品ページに行って商品を購入する」

このストーリーの場合、効果測定の方法によっては、「オウンドメディアの効果は良いけど、それ以外はあまり良くないね・・・」といった判断を下してしまう可能性もあります。
しかし、このストーリーからは、動画広告やリスティング広告経由のランディングページ、ネイティブアドのコンテンツなど、顧客が購入を決めるまでに多くのアプローチの効果があることがわかります。
ただ・・・効果測定結果の多くは、ここまで明快なストーリーを導くことは難しいのは現状だと思います。しかし、マーケターが想像力を大いに発揮して、ストーリーを作ることは大事ではないでしょうか?
マーケティングは、仮説検証の繰り返しです。タッチポイントを繋いでストーリーを作れば、次なるアクションが見え、成果を改善していくことができるはずです。
まとめ
今回は、タッチポイントにまつわる3つのTIPSをお伝えしました。タッチポイントが増えて、ますます複雑になっていくデジタルマーケティング施策ですが、ただ一つ変わらないのは「人」だと思います。
私たちマーケターは、人々の共感を呼び、行動に繋げるマーケティングプラン・クリエイティブを創造していかなくてはなりません。その繰り返しの結果、顧客の真の心に触れる(タッチする)ことができるのかもしれません。皆さんは、どう思いますか?
最後に:もしよかったら、ぜひFacebookファンになってください!
CONTACT
コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。
また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。