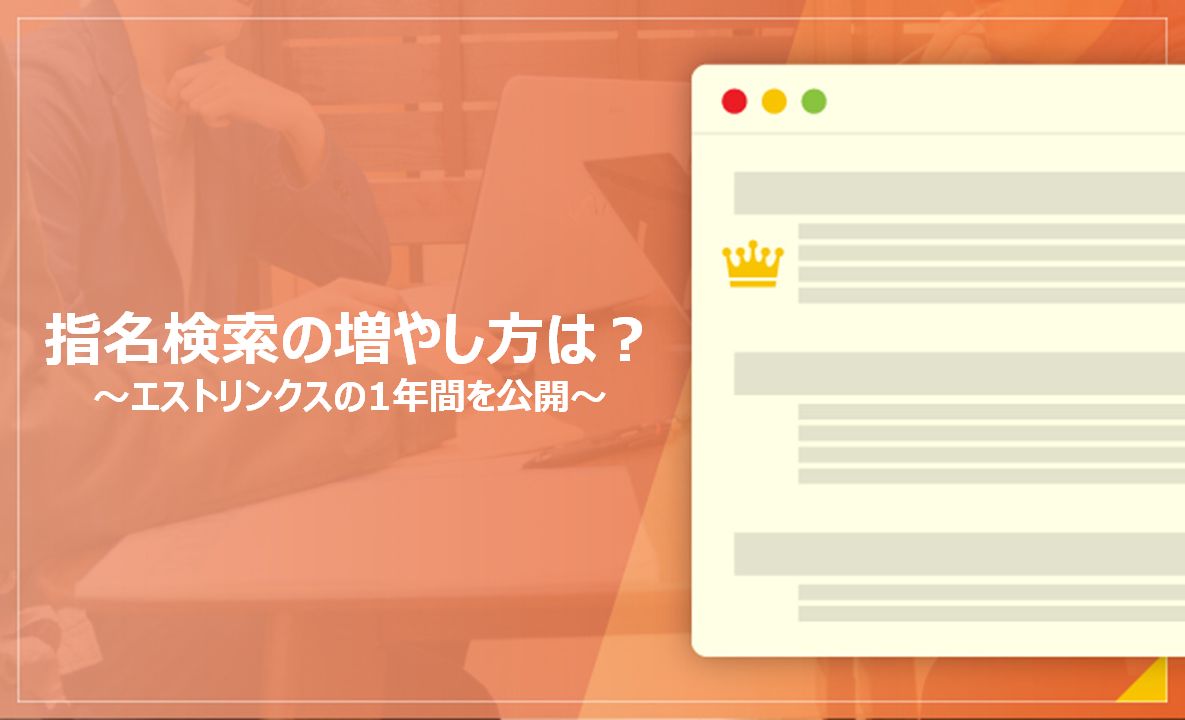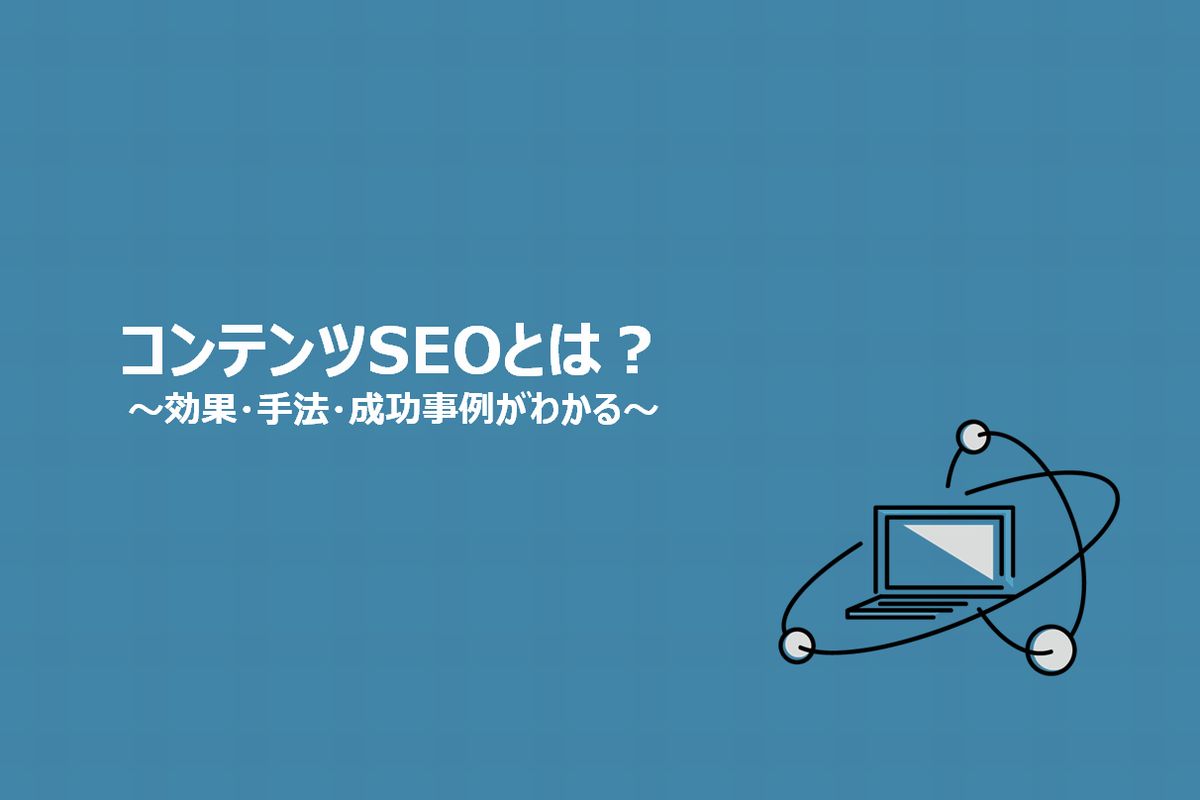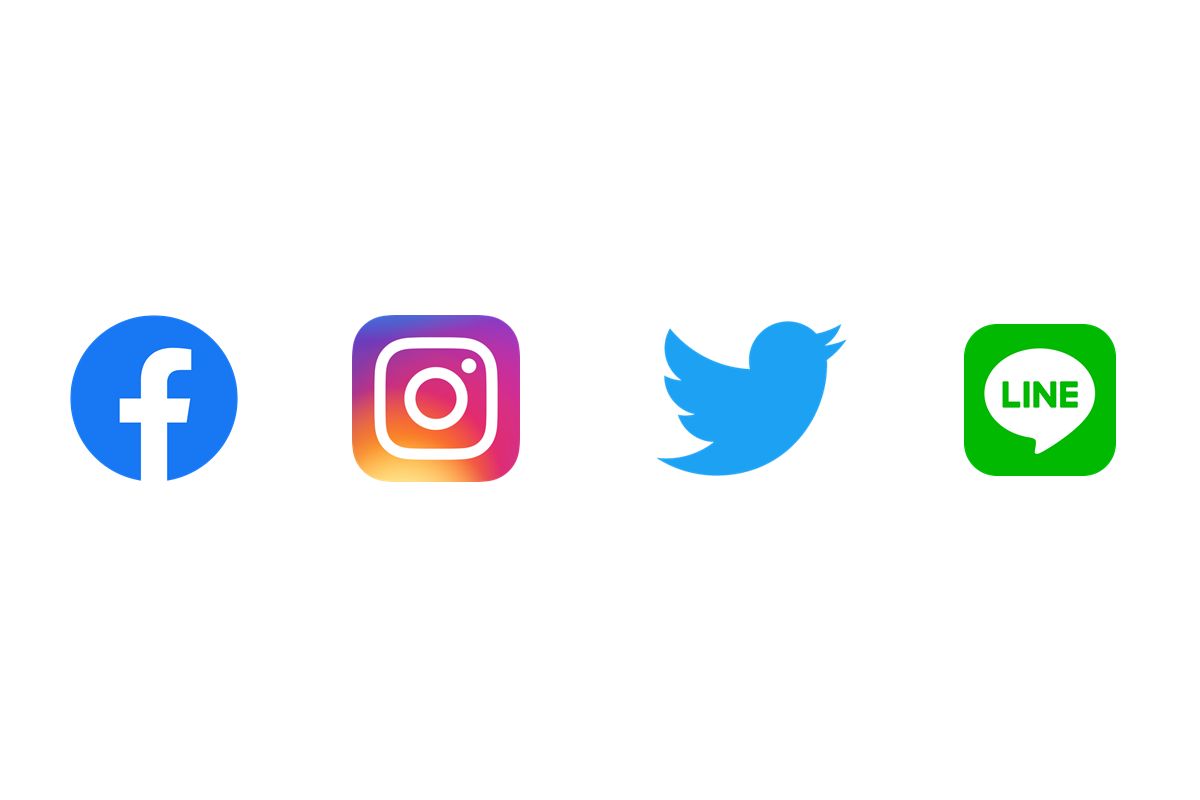監修者:山田新先生
静岡県静岡市生まれ。公認会計士試験合格後、2005年12月に中央青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)に入社。その後、株式会社ディー・エヌ・エー、都内の税理士法人を経て2014年3月に山田新公認会計士・税理士事務所を静岡市に設立、独立開業。法人個人の申告、相続税申告から会計監査、会計コンサルティングまで幅広くサービスを展開。事務所ホームページ:山田新公認会計士・税理士事務所
事業会社の担当者様から、「SEOってどうやって費用計上するの?」と聞かれることがあります。節税対策や社内決裁の兼ね合いから、どの勘定科目にして計上するかは意外と大切です。
オンライン集客を依頼するにあたって経理担当者様が気になるのは経費処理です。
この記事では、SEO(SEO対策)やホームページ制作・保守管理など、オンライン集客に関する費用について勘定科目をまとめました。
いままでお取引したお客様は、今回ご紹介するような経費処理をしていました。詳しくは各社の顧問税理士さんと確認するのがおすすめです。ちなみに、当社へのご依頼に限らずSEOを発注する前に『SEOとは?初心者にわかりやすく対策方法と仕組みを説明』をご覧いただくと、発注するメリットやデメリットが理解できます。ぜひご一読ください。
Contents
SEOにかかった費用の経費処理
SEOにかかった費用は広告宣伝費で計上するのが一般的です。ただし、コンサルティングやツール導入など、依頼内容によって勘定科目を変えたほうがわかりやすい場合もあります。
ここでは、SEOを広告宣伝費で計上するのが一般的な理由と、経費処理の仕訳例を紹介します。
SEOの仕訳例
SEOの経費処理をするときの勘定科目は「借方:広告宣伝費」「貸方:当座預金」で計上するのが一般的です。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
広告宣伝費 |
100,000 |
当座預金 |
100,000 |
ただし、SEOは複数の内容があるため、ガバナンス強化に努める会社では以下のように細目ごとに仕訳するのが正しいです。
たとえば、以下のように振り分けることができます。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
広告宣伝費 業務委託費 通信費 支払手数料 ソフトウエア |
50,000 30,000 5,000 5,000 10,000 |
当座預金 当座預金 当座預金 当座預金 当座預金 |
50,000 30,000 5,000 5,000 10,000 |
あらためて整理しますが仕訳を細目ごとに振り分ける場合、SEOに関連する料金は以下のように振り分けることができます。
- 広告宣伝費…SEOのために作ったコンテンツ制作費や被リンク獲得
- 業務委託費…SEOコンサルタントに支払う費用
- 通信費…ホームページ制作、ドメイン代、サーバー代
- 支払手数料…ホームページの保守管理費、SEOコンサルタントに支払う費用
- ソフトウエア…ホームページ制作の一部、SEOの分析に使ったツールの費用
このように、SEOの施策そのものは広告宣伝費でも、コンサルティングやツールにかかった費用やホームページ制作・維持にかかった費用は別の勘定科目で計上します。
現実には、SEOに関連する勘定科目はすべて広告宣伝費にまとめてしまうケースが多く見られます。会社の方針や顧問税理士さんの指導に従い、勘定科目を設定しましょう。
SEOの勘定科目の考え方
SEOはオンライン集客を目的とした経費なので広告宣伝費として扱うのが一般的です。そのため、経費処理をするときは減価償却の必要はありません。集客告知やSEOのためにコンテンツを頻繁に更新するホームページも広告宣伝費として扱えます。
SEOコンサルタントからオンライン集客に指導を受けた場合、SEOに関するコンサルティングなので業務委託費や外注費として計上しましょう。たとえば、弁護士さんや税理士さんなど士業の方に依頼するとき、勘定科目を業務委託費や支払手数料とするのと同じです。
ホームページ制作やドメイン・サーバーの取得や更新にかかる費用は、通信費またはソフトウエアとして計上します。ホームページテンプレートやECサイトの制作費用もここに含みましょう。
ホームページの制作費用は基本的に広告宣伝費や通信費として費用計上されますが、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、ソフトウエアとして計上し、その使用期間に応じて減価償却をすることとなります。
また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、ソフトウェアとして計上し、耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
なお、ホームページの保守管理費用は人の工数に支払う代金のため、支払手数料とするのが一般的です。
当社では、お客様が損をしないよう、ホームページ制作費をソフトウエアで計上する場合は広告宣伝費や減価償却についてお伝えしています。当社は、コンテンツを更新してSEOに取り組む会社なので、ホームページ制作も広告宣伝費で計上いただいて大丈夫です。
SEOを取り巻く源泉徴収税
当社はWEBライティング業を専門とする制作会社です。
過去、自社の経理が税法上問題ないか、国税局や税務署に確認したことがあります。
過去に以下のような回答をいただき、社内で電話の内容を記録しました。ただし、どの税理士さんに確認しても、最初は「原稿だから源泉徴収税の対象では?」と驚かれます。税法も日々変わっているので国税庁のホームページから確認することをおすすめします。
関連記事:チャットレディは副業でも確定申告は必要なの?納税の義務と申告手続きアプリ
源泉徴収税がかからない制作費
実は、WEBライターに記事を発注した会社が源泉徴収税を徴収する必要はありません。
執筆の仕事は原稿料に該当するため、源泉徴収税を徴収するのが一般的です。しかし、SEOを目的としたコンテンツ制作において、そのテキストは源泉徴収税に該当しないと東京国税局の方からご回答いただきました。
以下、国税局のホームページで掲載している原稿の報酬にWEBライティングが含まれていないからだと考えられます。
なお、WEBサイトの制作費(HTMLのコーディングを含む作業)も源泉徴収税の徴収は不要です。
本記事は2021年1月に執筆しました。もし税務署や国税局のご担当者が本記事をご覧になっていて法改正が行われた場合、ぜひその旨教えていただければ幸いです……。
源泉徴収税がかかる制作費
一方、WEBデザイナーに対しては源泉徴収税の徴収義務が生じます。
所得税基本通達204の7を読むと、デザインの範囲について定義されています。この中にWEBデザインは含まれていませんが、国税局の方からは「源泉徴収税の徴収義務が生じる」という回答でした。
HTMLコーディングを中心としたWEBサイトの制作には源泉徴収税はかかりません。しかし、デザインがメインになると源泉徴収税の義務が生じます。
ややこしいのですが、WEBサイトの制作がデザインを含んだものか確認しておきましょう。
参考:国税庁|〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕(デザインの範囲)
オンライン集客の経費は正しく計上しよう
SEOやホームページ制作など、オンライン集客に関する税法の仕組みは少し複雑です。節税のため依頼したのに、正しく計上しなかったばかりに予想より経費にできないこともあります。
今回ご紹介した情報をもとに、SEOに関連する経費処理を適切に進めてください。

山田先生からのコメント
源泉徴収をするのかどうかについては、実務でよく悩むポイントです。条文では源泉徴収が必要な支払いを細かく列挙しています(限定列挙)。ただし、ソフトウエアが無かった時代に作られた条文のため、現代に馴染まない職業や言い回しが使われており、そこで解釈の差が生じてしまうことで逆にわかりにくくなっています。実務は迷ったら源泉徴収する、というのも一案かと思われます。
初めてSEOを依頼しようと考えている方のうち、地方の方ならぜひ一度『地方の中小企業がSEOに取り組む意味ってあるの?メリット・費用対効果・怪しい電話営業の業者を見分けるコツ』のページをご覧ください。オンライン集客を焦っているときに「SEOを発注するのは本当に正しい選択か?」のヒントになれば幸いです。
CONTACT
コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。
また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。