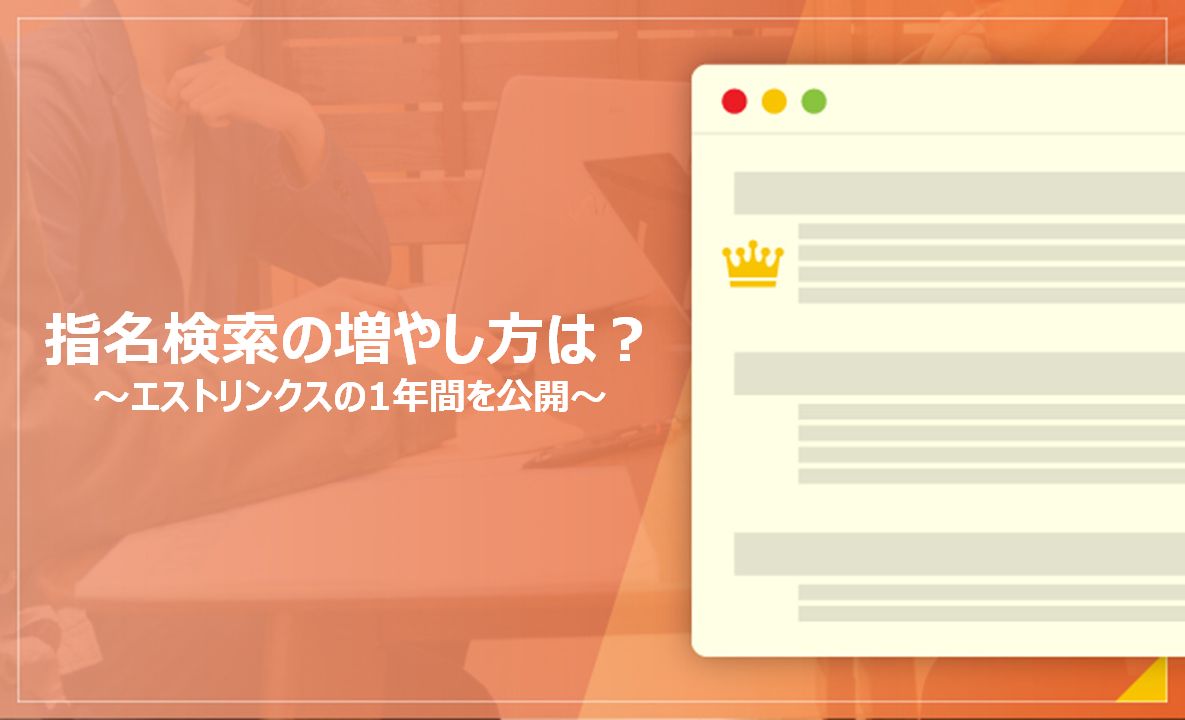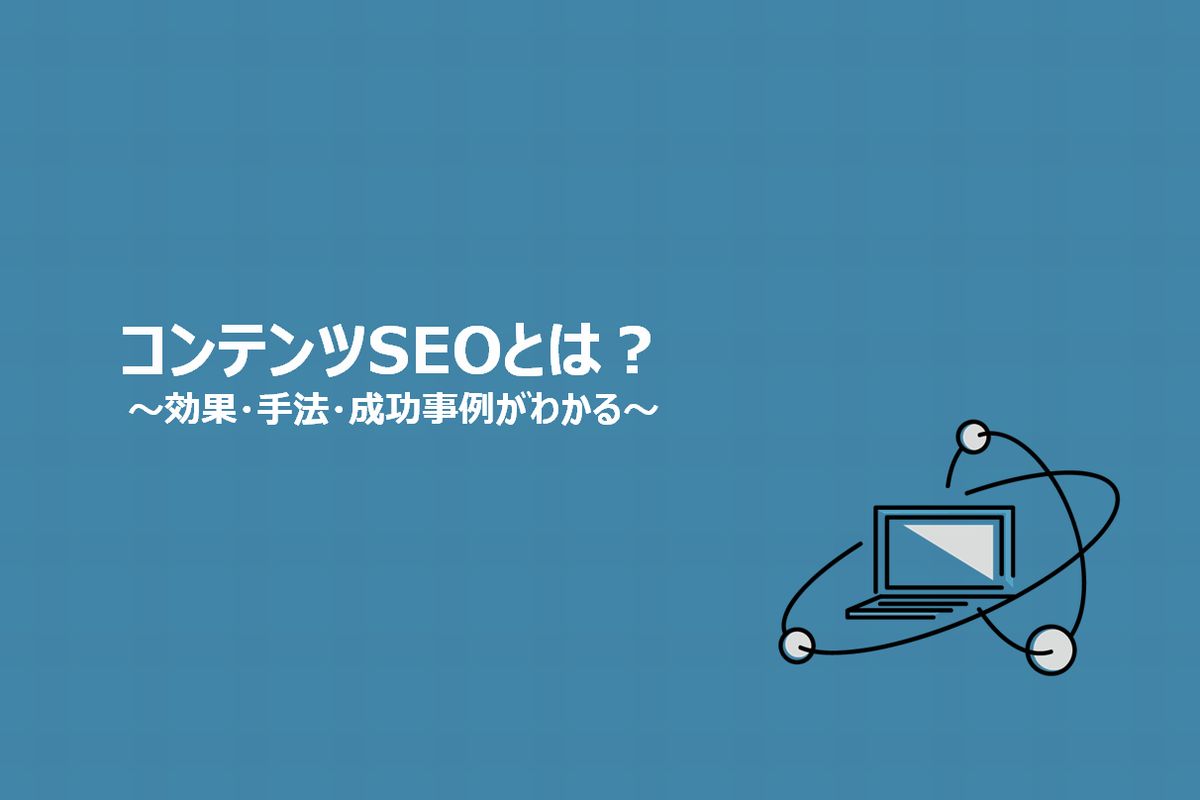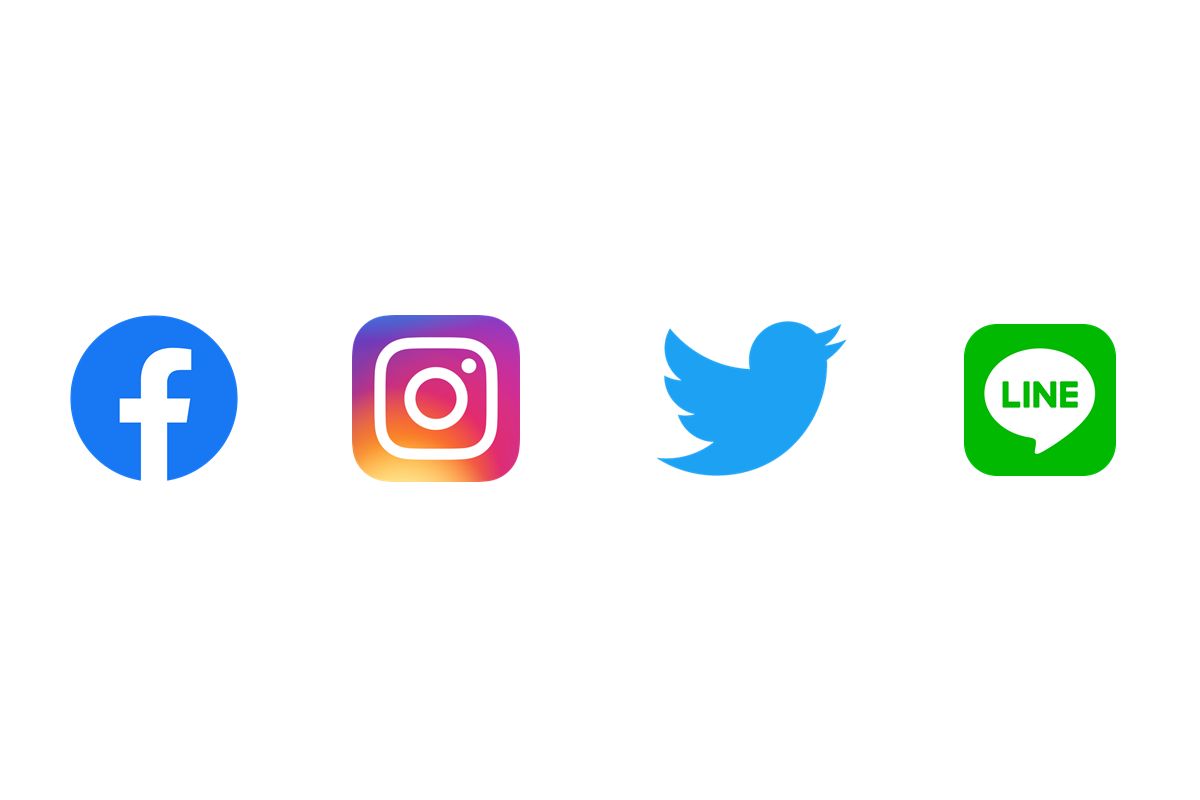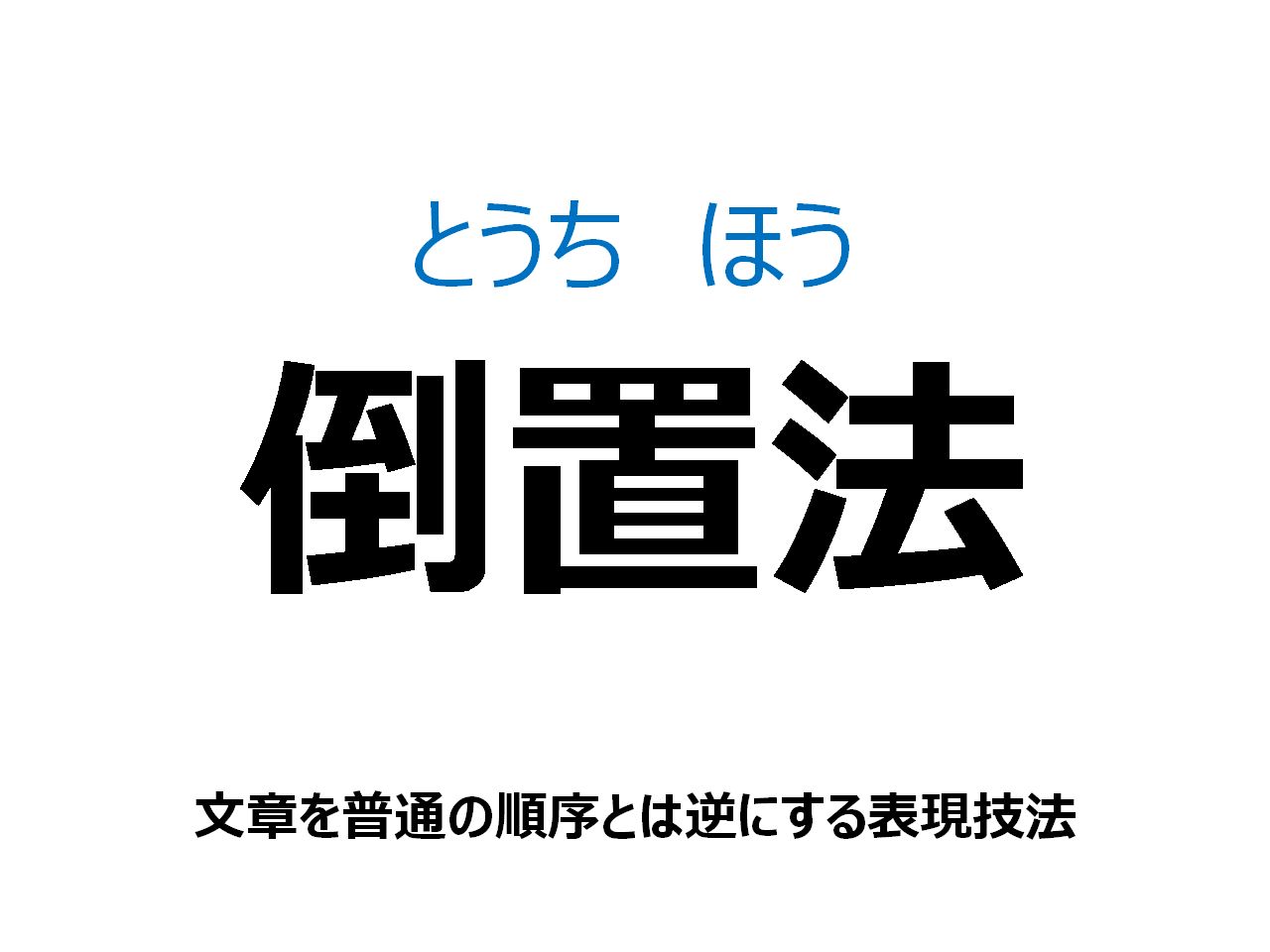
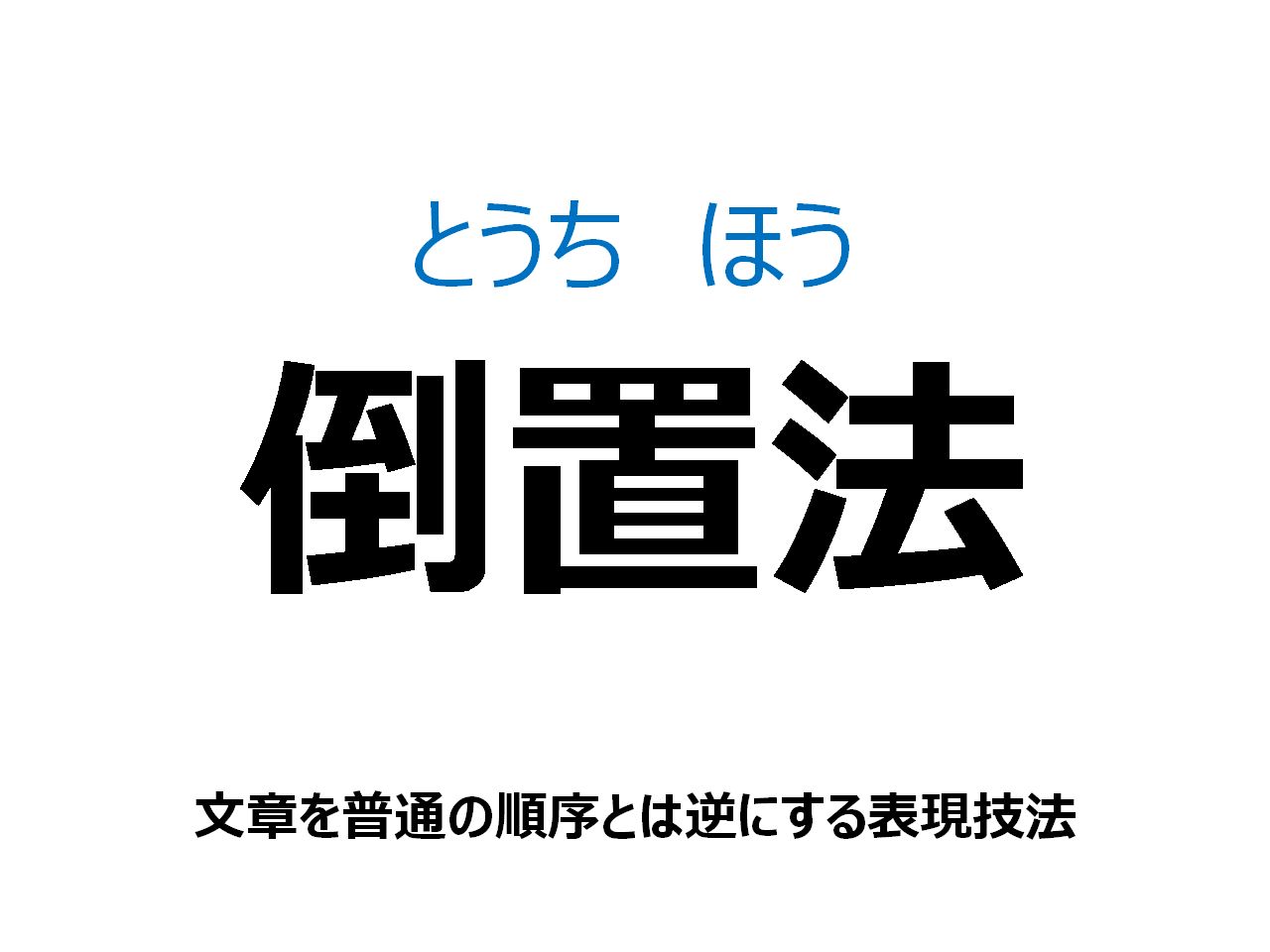
倒置法は通常の語順を変える表現技法の一種です。中学校の国語の授業で習った記憶がある人もいるのではないでしょうか?
この記事では、
これらをまとめました。より効果的に文章を印象に残す表現技法を学びたい方はぜひご覧ください。
Contents
倒置法とは
倒置法とは、文章の順序を変えて語調を整えたり語勢を強めたりするときに用いる表現技法です。俳句や短歌、詩、小説などで用いられます。
倒置の意味
倒置とは、さかさまに置くという意味があります。特に、文章表現において語順を反対にすることを指すのが一般的です。
日本語だけでなく英語でも倒置が使われていますが、否定や比較、感嘆などの意味があります。
この記事では、特に断りがない限りは日本語の倒置法を意味して話を進めます。
関連記事:国語の表現技法(修辞法)一覧
倒置法の例文・使い方・作り方

倒置法の使い方は文章の通常の語順を入れ替えるだけです。一般的に日本語の文章は「主語⇒目的語⇒述語」の順番で書きますが、倒置法を使った例文を見て比べてみましょう。
「彼女は海へ行ったよ。」
「俺はこの仕事が終わったら結婚するんだ。」
「この宿題を早く終わらせよう。」
「海へ行ったよ。彼女は。」
「この仕事が終わったら結婚するんだ。俺は。」
「早く終わらせよう。この宿題を。」
このように語順を入れ替えて作るのが倒置法です。
そのため、多くの場合は「●●は。」「××を。」といった語尾になります。
倒置法と体言止めの違いは?
倒置法と似た表現技法に体言止めがあります。
倒置法の多くは助詞(「~は」「~を」)で終わるのに対し、体言止めは字義通り必ず体言(名詞)で終わります。
普通の語順:私は友達と海へ遊びに行った。
倒置法:友達と海へ遊びに行った。私は。
体言止め:友達と海へ遊びに行った私。
どちらも文章を強調する効果がありますが、文章の終わり方が違います。余韻やリズム、文章の味わいが変わるため、詩や小説を書くときはより最適な技法を選ぶとよいでしょう。
関連記事:体言止めとは?例文・使い方・効果やビジネス文書で使うときの注意点
倒置法の効果

倒置法の主な効果は4つです。
- 強調する効果
- 語勢を強める効果
- 情緒的な表現をする効果
- リズムを整える効果
それぞれ見てみましょう。
強調する効果
倒置法によって目的語を最後に持ってくると、文章中の強調したい部分を読者に印象付けることができます。
最後に勝つんだよ、正義が。
普通の順序で「正義が最後に勝つんだよ」と表現するより、「正義」が強調された印象になります。
語勢を強める効果
倒置法により助詞で文章を終わらせると、語勢が強まる効果があります。
わかったぞ、犯人が。
「犯人がわかったぞ」と表現するのと比べて、語尾の強さが伝わるのではないでしょうか?小説で話者の強い感情を表現するときにも倒置法は活躍します。
情緒的な表現をする効果
倒置法は情緒的な表現をする効果もあります。
遠くで聞こえる、汽笛の音が……。
「汽笛の音が遠くで聞こえる」と表現するのと比べて、汽笛の音の余韻を感じませんか?
倒置法が詩や小説でしばしば使われる理由は、このように読者へイメージさせる効果があるからです。
リズムを整える効果

文章のリズムを整える効果もあるのが倒置法です。たとえば、短歌や俳句、詩、歌詞など、字数制限があったり語尾の韻を統一したりしたいときがあると思います。
「毎年よ 彼岸の入りに 寒いのは」(正岡子規)
彼岸の入りに寒いのは毎年のことですが、通常の語順では趣も出ずリズムも出ません。「毎年よ」と始まり「寒いのは」と終わることで、リズムが際立ち、かつ情緒のある俳句になるのです。
倒置法で面白い文章を作ろう
倒置法を使うと文章の雰囲気ががらりと変わります。多用しすぎると意味が通じにくいですが、ここぞというタイミングで語順を変えると非常に印象的です。倒置法を使って文章に奥行きを持たせてみましょう。
CONTACT
コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。
また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。